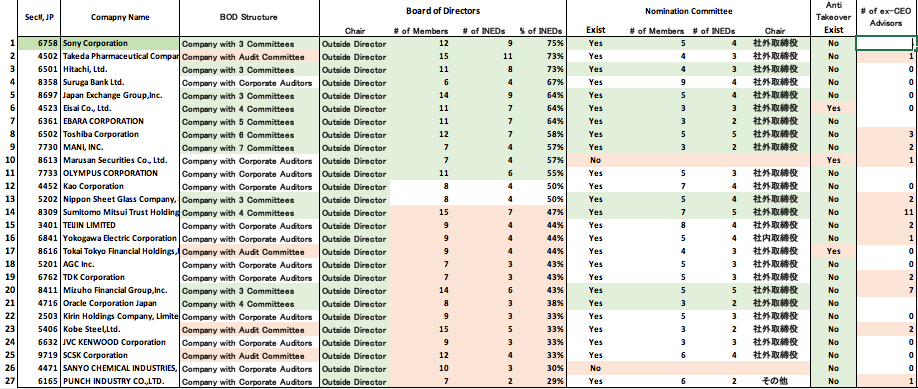日本の役員研修を支援する機関投資家のほとんどが日本の機関投資家ではなく海外の機関投資家というのはいったいどういうことでしょうか?
公益社団法人会社役員育成機構(BDTI)は、「公共・公益に資する」非営利団体として設立しました。日本の市場に必要な役員・ガバナンス研修を質が高くかつ低価格で提供し、こうした役員・ガバナンス研修を日本でも広く普及させるために、 日本の機関投資家も 非課税で支援することが出来る組織として設計し、そのために公益認定を申請しました。しかし、その難しいプロセスを経てBDTIが公益の認可を取得して以降8年たちますが、機関投資家からの寄付金の95%は海外の機関投資家あるいはファンド・マネジャーによるもので、日本の機関投資家からの寄付金は5%未満にとどまっています。しかも日本機関投資家上位30社からの寄付は全くありません。