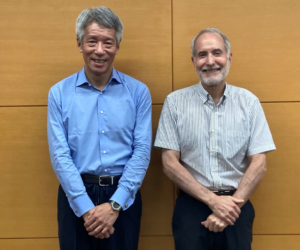本年度も女性のための役員研修奨学金制度を実施いたします。投資運用会社オアシスマネジマントは4年連続で、BDTI主催の役員研修に協賛し、優秀な女性に奨学金を提供する取り組みを実施します。BDTIの対象役員研修コースのいずれかを申し込んだ優れた資質を持つ女性に対し、スポンサー企業のオアシスが受講料を全額負担します。この支援の目的は、高い資質を持つ女性リーダーが取締役として活躍するために、研修によって必要なスキルを身につけ、女性取締役候補のパイプラインを拡大することで日本の取締役のジェンダーギャップに積極的に対処することです。BDTIの研修は、コーポレートガバナンスの知識を早めに習得する機会となり、将来の役員人材を確保するうえで、企業にとっても機関投資家にとっても有益です。奨学金制度を通じて、多くの女性が役員研修を受講するきっかけになることを期待します。次世代の女性リーダーとしての第一歩を踏み出してください!