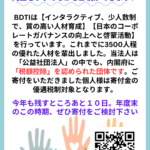の役割とは何か-1-1-300x161.png)
第一生命保険株式会社取締役会長兼GFANZ日本支部コンサルテーティブ議長が語る
グラスゴー金融同盟(GFANZ)の役割とは何か
GFANZは2050年までに世界の温室効果ガス排出量のネットゼロへの移行を加速し、地球温暖化を1.5度以下に抑えるというパリ協定の目標達成に向けた、金融機関・機関投資家およびその部門別連合による専門家主導のグローバル連合です。銀行、保険会社、アセット・オーナー、資産運用会社、ベンチャーキャピタリスト、金融サービスプロバイダー、投資コンサルタントなどの金融セクターから、50カ国・地域における675以上の企業がGFANZのコミュニティに属しており、これは世界の民間金融資産の約40%を占めています。