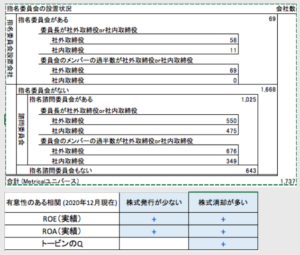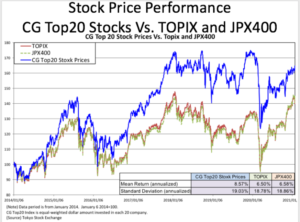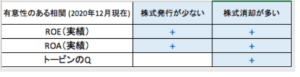令和3年2月15日(月)「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」(第24回)が開催されました。
その中で、有識者会議のメンバーとしてICGNの最高経営責任者ケリー・ワリング氏が意見書を提出しました。
今回の意見書は、有識者会議の議題として記載されている以下の項目に対応しています。
1. 持続可能性と気候変動
2. 持続可能性と社会的不平等
3. 企業と投資家の対話を充実させるための施策
3. 「企業と投資家の対話を充実させるための施策」の中で、取締役が研修活動に参加することの重要性が謳われています。(以下、意見書より抜粋)
3.3 取締役の能力構築
ICGN は、日本の企業に対し、取締役会の責任を行使する際の実効性を高めるために、執 行役員及び独立社外取締役を問わず、すべての取締役が高水準のコーポレート・ガバナ ンスについて教育を受けることにコミットすることを奨励しています。私たちは、企業 が取締役のための研修方針を開示し、適切な期間に実際にどのような研修が行われたか を報告することを奨励しています。
ICGN はまた、日本の企業に対し、すべての新任取締役が就任後できるだけ早く会社に ついて十分な情報を得られるように、正式な導入プロセスを持つことを奨励しています。 これには、会社の戦略、事業運営、規制上の義務、その他の基本的なビジネスの推進力 についての理解を深めることが含まれます。




 >
>