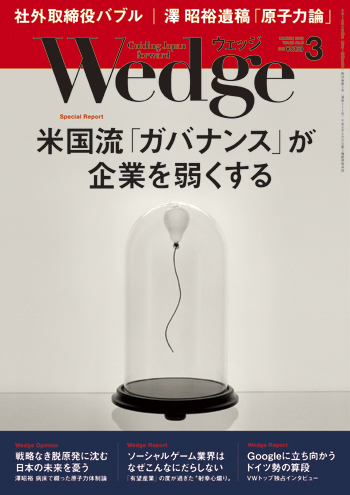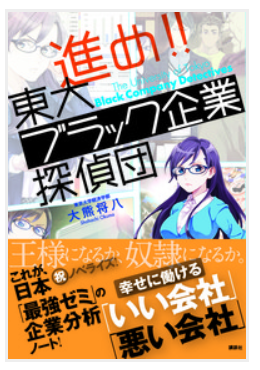http://www.sophia.ac.jp/jpn/info/news/2015/11/globalnews_1659/20151101 昨年11月に上智大学が日本の大学基金として初めて国連責任投資原則(PRI)に署 […]
RIETI:「グローバル・ガバナンスの今後-COP21「パリ協定」合意に見る「一筋の光明」-」

「12月12日、厳戒態勢のパリにおいて開催された国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)は、世界の気温上昇を2℃未満に抑えるための取組などを盛り込んだ「パリ協定」を採択した。本協定は、2009年のCOP15において採択された「コペンハーゲン合意」のような政治合意とは異なり、れっきとした法的文書である。同様に法的文書である「京都議定書」(1997年のCOP3で採択)の後継協定となるが、同議定書とは異なり、加盟各国の温室効果ガス排出削減目標に関して法的拘束力がないことが、今次「パリ協定」の最大の特徴の1つである。
筆者は気候変動の専門家ではないので、「パリ協定」の内容の当否について論ずることは控えたいが、グローバル・ガバナンスに日頃より強い関心を有する立場から一言述べたい。
RIETI:「原子力改革の遅れ 挽回を」
「今年3月で、東京電力福島第1原子力発電所の事故から5年の歳月が経過する。同事故が国民的課題として突き付けたエネルギー政策の根本的見直しは進展しているのだろうか。結論を先取りすれば、エネルギー改革の到達点は分野ごとに大きく異なっておりまだら模様である。肝心の原子力改革については目立った進展がみられないなど、全体としては残された課題の方が大きいと言える。
RIETI:「日本における取締役会の改革の効果分析」
「カネボウ、ライブドア、オリンパスなど、日本企業の不祥事が相次いだ。内部者によって構成されている取締役会は企業のパフォーマンスと関係なく社長を選任し、そのように選任された社長は企業価値を高めるような経営をすることは難しい。このような日本企業のコーポレート・ガバナンスの問題を解決するために、外部取締役と経営者の誘因メカニズムなどを中心とするアメリカの企業統治方式を日本へ導入する方向へ改革が行われてきた。具体的な改革措置は2001年の社外取締役導入、2003年の委員会等設置会社の導入、更には2006年施行の会社法による、会社の規模に関わらない委員会設置会社への移行であった。しかし、2003年に委員会設置会社へ移行した東芝で最近起きた不適切会計の問題はコーポレート・ガバナンスの制度を変えることだけでは日本企業の経営を新たにできないことを示唆する。今年また会社法が改訂されたが、その前に行われた一連の改革措置が日本企業のパフォーマンスにどのような影響をもたらしたかについて、2005年から2010年までの『企業活動基本調査』の個票データを用いて分析した。
RIETI:「パリ協定の採択と今後の地球温暖化対策の展望」
RIETI:「ダイバーシティ経営とワーク・ライフ・バランス」
日本社会の面するもっとも大きい長期的な制約は少子化である。これは高齢人口の拡大と相まって日本経済の中長期的観点からの最大の成長制約要因でもある。経済成長制約緩和の重要な処方箋の1つは、先進国標準から大きくかい離した(ゆえに潜在力も大きい)女性就労の水準を量・質ともに大幅に改善することである。しかし女性が子どもを持つ意欲を実現できるような雇用慣行の形成を同時に伴わなければ日本の長期制約は緩和されるはずもない。
この両者を含めた概念としてのダイバーシティ経営に視点をあて、シンポジウムでは、女性活躍を中心としたダイバーシティ推進及びそのための環境整備としてのワーク・ライフ・バランス(WLB)に向けた個々の企業の取り組みや政府の施策が企業経営に、また女性の賃金や働き方にどのような影響を与えているか、効率性の視点から、また個人の行動に見られる選択の側面から議論する。
大熊将八著:「進め!東大ブラック企業探偵団」
QUICK ESG:「【コーポレート・ガバナンス】<2/19更新>東証「改正規程」に基づき報告書を開示した上場会社」
2015年12月25日以降2016年2月19日までに報告書を発表した企業をまとめた(2015年6月1日からの累計は1916社:社数は更新による重複を除く実質発表企業数)。
また、新様式で報告した企業が増加したため、報告書を開示した企業を別ページにまとめている・・・。」