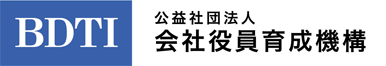「12月12日、厳戒態勢のパリにおいて開催された国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)は、世界の気温上昇を2℃未満に抑えるための取組などを盛り込んだ「パリ協定」を採択した。本協定は、2009年のCOP15において採択された「コペンハーゲン合意」のような政治合意とは異なり、れっきとした法的文書である。同様に法的文書である「京都議定書」(1997年のCOP3で採択)の後継協定となるが、同議定書とは異なり、加盟各国の温室効果ガス排出削減目標に関して法的拘束力がないことが、今次「パリ協定」の最大の特徴の1つである。
筆者は気候変動の専門家ではないので、「パリ協定」の内容の当否について論ずることは控えたいが、グローバル・ガバナンスに日頃より強い関心を有する立場から一言述べたい。
「パリ協定」は議会承認手続の回避を至上命題とする米国政府の方針の所産
今回のCOP21に至る道程および同会議の会議場内外における諸経過は、いずれ詳細が明らかになっていくのであろうが、これまでの報道を見る限りでは、米国が、気候変動を最重要課題の1つと位置づけるオバマ大統領の方針の下、野心的でありながらも米国が受諾可能な協定内容とするために、各国との交渉において政治資源を最大限駆使したことが伺える。米国政府が国際合意を受諾するに当たっての最大の障害は、何と言っても米国議会である。この構図は、気候変動のみならず、たとえば、通商(TPPの締結に必要なTPA(貿易促進権限)法案やTPP大筋合意内容の承認を巡っての議会の厳しい対応)や国際金融(新興国のクオータ配分や投票権を高めるIMF改革案に対する議会の反対)など、米国の外交政策全般において頻繁に見られる現象である(このような米国議会の姿勢は、往々にして、中国等新興国の台頭に象徴される国際政治の「多極化」現象に対する内向的な反応という側面がある)。今回のCOP21に際しては、米国議会(特に過半数を占める共和党)は、関連産業の利害および新興国との義務の均衡という観点から、その展開に対して厳しい目を光らせていた。米国が新たな法的義務を負う合意内容となれば議会承認を必要とするため、米国政府は、先進国のみならず全加盟国が責任を負うべきことや、各国別の排出量削減義務および新たな資金拠出については法的拘束性の対象外とするべきことを主張し、実際、「パリ協定」はそのような内容で妥結した・・・。」