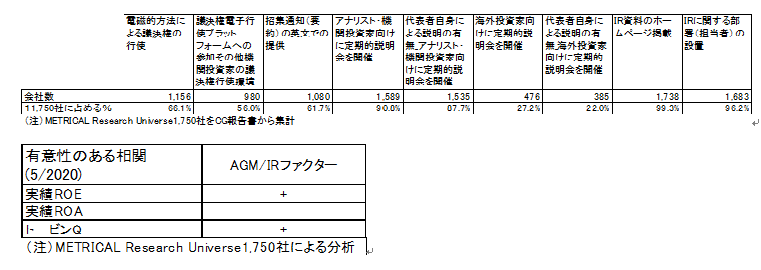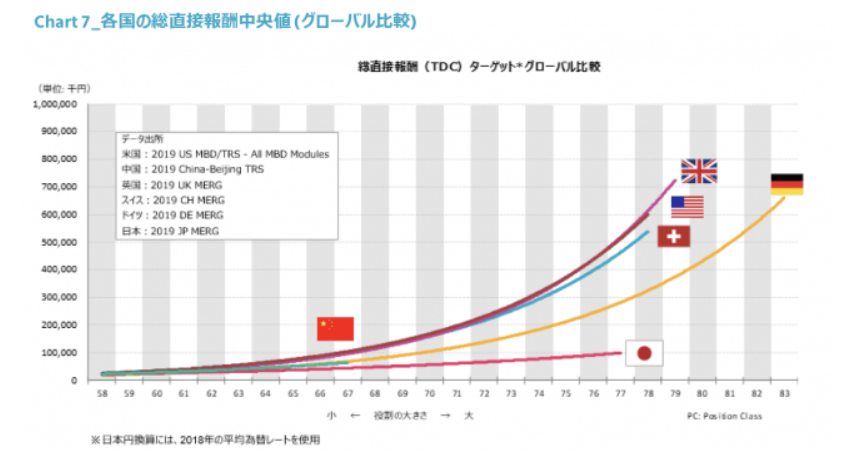(訳20年前に書かれました。)「…これまで一般に言われてきた日本企業のコーポレートガバナンスの特徴を要約すると、①内部昇進者による取締役会・監査役会の運営、②企業間の株式持合による安定株主化、③メインバンクによる支援体制、といった点があげられる。これらの仕組みは、敵対的な買収を防止し経営の安定化を促進し、企業の長期的な戦略立案を可能にするなど、日本的経営が成功した要因の一つとして評価されてきた。
しかし、取締役や監査役の大部分が内部昇進者で占められ、社長が両者の実質的任免権を持つことにより、取締役会や監査役が利害関係者の集団にとどまってしまい、企業トップ自身が不祥事に深く関わるような場合には、経営に対するチェック機能が働かないという深刻な問題が浮き彫りになってきた。また、株式持合の進行により、互いの経営内容について口を挟まぬ「物言わぬ株主」を増加させ、資本市場からのチェック機能の不全化も招いた。このような経営のチェック機能の弱体化と併せて、株主の権利の軽視や低い投資収益率についての批判もなされるようになった。