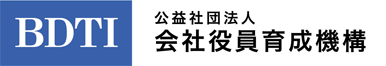本号からお読み頂く方のために。BDTIは、日米のクラスアクションを比較し、日本企業が取り組むべきリスク管理を考えるセミナーを2017年1月に実施した。多くの有意義な提言がなされたが、同時にクラスアクションを研究する場の必要性も認識された。こうして始まったのが、本研究会であり、研究成果をまとめたのが本報告書である。(第1号はこちら)(第2号はこちら)
Ⅰ. 本研究会の目的目的
Ⅱ. 本研究報告書の利用上の注意と構成
Ⅲ. 日米クラスアクション制度の俯瞰
Ⅳ. 米国クラスアクション制度の概要と実務上の問題
1. 国におけるクラスアクションとは
2. 米国におけるクラスアクションの動向
3. クラスアクション手続の概要
4. クラスアクションにおける証拠開示手続をめぐる問題(以下本号)
5. クラスアクションの防御戦略(以上本号)
6. クラスアクションの和解戦略
7. 和解と経営判断-企業存続にかかわる事態を避けるために
Ⅴ. 新法によるわが国制度の概要と実務上の問題点
1. 新法制度の背景
2. 新法の特徴
3. 新法による手続の流れ
4. 特定適格消費者団体
5. 新法のリスクと対象事案のイメージ
6. 考えられる対策
本報告書関係者の紹介
本号がカバーする部分の監修者と、本研究会座長をBDTIから紹介する。
須藤希祥弁護士 長島・大野・常松法律事務所アソシエイト
https://www.noandt.com/data/lawyer/index/id/1716
消費者庁に出向し、日本版クラスアクション法の制定作業に携わった経験を有し、立法化の過程で持ち上がった、大小ありとあらゆる論点を把握している。日本版クラスアクションは、複雑な訴訟手続と論点を有しており、これまでの民事訴訟の延長ではないから、今後提起されるであろう日本初のクラスアクションには、須藤氏のような専門家の支援が必須であろう。研究会はいち早く支援を受けることができた。
研究会座長:島岡聖也
長年に亘り株式会社東芝の法務畑を歩み、米国でパソコン等製造物、品質責任に関するクラスアクションを多数経験している。合法的な恐喝とすら評されることのある裁判を経験し、普段から企業がとるべき手続、弁護士との戦略会議、土壇場の意思決定に関し助言できる数少ない実務家であり、その経験を我が国の企業法務に役立てたいという意思を持つ。研究会の立上げから成果物執筆まで、座長としてリーダーシップをとった。
前号からの続き
報告書本文
6.クラスアクションの和解戦略
⑴ クラスアクションにおける和解の意義と不当類型
クラスアクションの解決にとって、和解の位置づけとその果たす役割は量的にも質的にも非常に大きく、その手続的適正性の保障だけでなく、実質的な公正性、合理性、妥当性の確保を巡る議論は様々な変遷をたどってきた。
➀ クラスアクションと和解の位置付けの変遷
オプトアウト型クラスアクションが一般化され、さまざまな類型の多数被害について集団的な救済への道が開かれた、特に1980年代から、クラスアクションは激増し、また、大型化・複雑化していくようになった。その結果、さまざまな産業で巨大な法的責任に耐えられず、いわゆるPL保険の危機、企業倒産や場合によっては業界全体への大打撃(たとえば化学製品、アスベスト、たばこ、医療用具が有名である)に至るなど、クラスアクションは産業の競争力・存立に無視できない影響を与えることとなった。そして、上述した通り、米国特有の司法制度やその運用の問題から、莫大な労力や資金を必要とするだけでなく、陪審制度の性格上、評決結果やそのインパクトを正確に予測することは非常に困難であることから、陪審評決に勝敗を賭けることは、被告にとっては会社の存立をも危うくする恐れがある一方、原告にとっても費用倒れのリスクの高いギャンブルとなるといわれてきた。そのために、できるだけコスト、リスクを避けて和解するという動機は両当事者にあり、特に大型事件になるほど和解による解決が促進された。
その一方で、露骨なパワーバランスを背景とした濫用が指摘されるにいたった。その議論の概要は以下の通りである。
ⅰ)不当和解類型
クラスアクション和解を巡る議論のうち、制度濫用の観点でもっとも議論され、争われてきたのは、いわゆる不当な和解の存在を認めるか、また、その防止としてどのような規律が必要かという点であったと思われる。
不当な和解といわれる類型としては、被告側からは、原告側から恐喝的に和解に追い込まれるBLACKMAIL SETTLEMENT(恐喝的和解)が指摘される一方、消費者保護の観点からは、クラス構成員(特にABSENT CLASS MEMBERと呼ばれる代表原告以外の多くの対象消費者)の利益を犠牲にして原告弁護士・代表原告と被告弁護士・被告事業者が通謀してその利益を優先し、クラス全体が有すべき本来の救済価値に見合わない和解(それに引きかえ多くの場合原告弁護士の報酬は過大である)を行うSWEETHEART SETTLEMENT(通謀的和解)が横行したといわれる。
ア.BLACKMAIL SETTLEMENT
BLACKMAIL SETTLEMENTについては、クラスアクションの和解プロセスにおいて、アメリカの訴訟手続に関連する特有の制度、手続や、従来のクラス認定の要件の緩さから、代表原告は本案に関する十分な主張・証拠は有していないのに、代表原告に有利な裁判所を選び(FORUM SHOPPING)、「陪審によるトライアルに移行すれば原告側の主張は簡単に通り、懲罰的賠償を含む莫大な損害賠償義務を負い倒産の危機に陥ることになる」と圧力をかけて、強引に原告に有利な和解に引き込むというもので、原告弁護士による濫用の典型であるといわれた。
この立場では、特にリスクの高い大規模事案の和解率の高さや原告弁護士の立証活動の実態に比べ著しく高い報酬額とは対照的に、対象消費者の和解条件による救済額の低さや応答率(TAKE-UP RATEまたはREDEMPTION RATEといわれる)の低さは、まさに消費者を救済すべき実体のない(MERITLESS、FRIVOLOUS)和解を推測させるものであるという。しかし、原告の立場からは、このような決めつけは幻想にすぎず、零細な原告の集団をまとめコストもリスクも大きいのは明らかに原告側であり、豊富な資金力と練達した弁護士をそろえて戦う被告事業者が和解に応じるのは、抑圧されて応じるのではなく、見込みのないギャンブルを避けるために行うもので、このような非難は事実と異なる誇張であると主張する。
一方、法政策的な意味でも、クラスアクションの目的には、被害の回復だけでなく、「私人の法執行による消費者共通の公益的な価値の保護(再発抑止や悪質企業への制裁を含む)」という理想があり、その意義は可能な限り実現されるべきであるといわれる。上記の濫用に関する議論や、後述する「和解目的クラスアクション」の是非を巡り未だに論争は続いていることの背景には、このようなクラスアクションの持つ公的な役割論(代表的にはいわゆるPRIVATE ATTORNEY GENERAL論[1])をどのくらい重視するかという理念の対立があると思われる。[1]特に市民権、労働、環境等の分野では、私人(弁護士)がいわば私的司法長官として私人による公益の実現を認める法制度があり、特に費用等を一定の範囲で、相手方に負担させる(双方が分担するいわゆるアメリカンルールの例外)として、訴訟提起を容易にする制度になっている。クラスアクションはその範疇に入るか否かについては、クラスアクションの性格上、公益だけでなく弁護士のビジネスの要素も強く、いったんは判例上否定はされているが、その後も様々な議論がなされている。
イ.SWEETHEART SETTLEMENT
他方、SWEETHEART SETTLEMENTは上述した通り、クラス全体の利益をないがしろにしたうえで、原告・被告の交渉関係者が通謀して、被告にとっては最も有利な和解内容を認めることと引き換えに、一部の原告関係者、特に代表原告と原告弁護士には過大な利益を与えるというものである。1990年代に至り、大規模不法行為クラスアクションが一般化していく中で、さらに、REVERSE AUCTION SETTLEMENTという被告優位の、より悪質な類型が現れたといわれている。すなわち、多数のグループに分かれてそれぞれ別の原告弁護士が主導権を巡り競合する大規模不法行為案件等において、被告がこれらの原告弁護士と交渉を重ねるうちに、被告にとって最も有利な条件を示す原告弁護士・代表原告と通謀の上、その交渉を先に成立させ、それを全体の和解として拡張して被告の利益の最大化を図る一方、その見返りとして代表原告弁護士の弁護士費用や原告グループへの救済は厚遇する目的をもって和解をすすめるというものである。
これらの濫用の防止は、事案を主として担当する裁判官(手続の開始から陪審審理、判決までを通して担当するのが通例である。以下、主任裁判官という)自身が和解条件の決定や和解承認にあたり最も注意する事項の一つであり、このような米国クラスアクションの和解の公正性、合理性、妥当性の確保の要請は、米国クラスアクションの和解の在り方を理解するにあたり、必須の事項である。
なお、米国においては、主任裁判官は自ら和解や調停を担当することは適切ではないとされ、このような手続では主任裁判官の指示によりMAGISTRATE JUDGEまたは経験豊富な退任判事や弁護士がMEDIATORとしてこれに当たることが多い。
⑵ 和解のタイミングと裁判所の姿勢
米国においては、当事者主義を前提に、従来、和解を含めた訴訟の処分については当事者の意思に任され裁判所が和解の勧試を行うことはあまりないといわれてきた。しかし、クラスアクションや大規模不法行為訴訟の急増により、全米にまたがる訴訟数も急増し、州裁判所ごとの判断の不一致を避けたトータルな解決策の要請も高まり、そのための裁判所の負担も急増したことから、特に複雑大規模訴訟(COMPLEX LITIGATION)では、主任裁判官は裁判手続の冒頭から積極的に和解の勧試を行い、また、和解の推進のための様々な工夫がなされる。
上記の通り、和解にはパワーバランスが色濃く反映されるが、クラスアクションの関係者の義務として、代表原告およびその弁護士はクラス全体の公正かつ公平な利益の保護のために注意義務を負い、さらに裁判所の役割はクラス構成員、特に代表原告以外の多数のメンバーの後見人的役割を果たすことにあるとされているために、米国ではクラスアクションの取下げ、和解等の終結についてすべて裁判所が関与して、和解の予備承認の後、関係者への通知、オプトアウト、最終ヒアリングでのクラス構成員からの異議申述の機会を保障したうえで、裁判所が和解を最終承認することが必要であるとされる。裁判所はこれら和解等については手続的適正だけでなく、連邦規則23条に定める成立要件はもとより、実体的な公正性、妥当性、合理性が確保されているかを確認し、最終承認する義務を負う。
*わが国においては、裁判上の和解の手続としては、米国と異なり裁判官(判決を書く裁判官[2]。)[2] わが国の民事訴訟でも、手続を主宰する合議の裁判所(受訴裁判所)のうちの一人が和解の担当となる(受命裁判官)場合や、他の裁判所の裁判官が委託を受けて行う(受託裁判官)場合があるが、米国と異なり、判決等の意思決定を行う裁判官が和解等の手続に関与すべきでないという考え方はない。が判決に関する心証開示を含めた和解の勧試を行うことができる。このような事実上の説得力を背景に和解が成立した時には、和解調書に署名しなければ成立しないという意味では承認権限を持っているともいえるが、元来、裁判上の和解も本質的には和解契約である以上、公序良俗違反を含む違法な要素がない限り、極力当事者の意思が尊重される(もちろん実質的に、受訴裁判官の心証に照らして著しく不公平、不合理な和解について事実上承認することはないと思われる)。新法における訴訟に関して、裁判所が和解にどのような姿勢をとるか、従来の実務によるのかどうかを見守る必要がある(共通義務確認訴訟において柔軟な和解が困難であることについては後述参照)。
それでは、和解がどのような時期にどのようなパワーバランスでなされ、これをどのように具体的に規律しようとしているのか、全体の流れとともに、連邦裁判官のハンドブック(MANUAL FOR COMPLEX LITIGATION,4th ed.)を手掛かりに、簡単に述べてみたい。
➀訴訟提起当初からクラス認定まで
通常、クラスアクションが提起された直後に、いわゆるプリーディング手続(冒頭の書類のやり取り)で、訴状送達、訴答、さまざまなMOTIONが出され、争点が整理されながら、裁判所は両当事者を呼び(INITIAL SCHEDULE CONFERENCE:最初のスケジュール協議)、全体スケジュールを調整する。その要点は、整理された争点に関するディスカバリーのタイミングと内容、専門家証人による陳述、法律論点に関する略式判決(SUMMERY JUDGEMENT)、クラス認定のための陳述と申請手続というクラス認定までのプレトライアル手続と、クラスが認定された後の陪審審理に至る手続に関するトライアル手続に大別される。
かつては、クラス認定までの間は、当事者主義の下で、いずれかの当事者から異論や遅延が出ない限り、やり取りは当事者の自治に任され、裁判所は手続の進行監視を行うだけの役割を担うというのが裁判所の基本スタンスであった。しかし、現在の実務は、まず、最初のスケジュール協議の際に、両当事者に対して、和解が進んでいるかまたは今後検討する予定があるかを確認し、その後も和解による解決を成功させるために、中立性を失うことなくさまざまな働きかけを行うべきであるとされている。しかし、当事者にとっては、ディスカバリーがある程度進むまでは、いわゆるHOT DOCUMENTや重要証人の存在は明らかでない場合も多く、事案の全体像は当事者自身ですら理解していない場合もあるので、よほど責任が明確か、根拠がない請求でもない限り、和解の契機となることは少なく、その時点で裁判所も和解を勧告することはまれである。しかし、裁判所は、当事者は裁判所と密に連携しながら、訴訟の進行に合わせて和解協議を進めることを勧奨し、そのために必要であれば、当事者の申立てがなくても当事者同意のもと和解協議に当たらせるため、主任裁判官が監督する他の中立の裁判官(MAGISTRATE JUDGE)や和解専門家(SPECIAL MASTER、MEDIATOR)を任命したり、一定期間他の見識あるADR機関(たとえばJAMSやABA)による和解協議に付したり、スケジュールの進行の調整を行う。
実際に和解の契機となるかどうかという意味では、ディスカバリーの果たす役割は非常に大きい。ディスカバリーが進めば、事案の性格や有利不利はおのずと明らかになり和解の契機となるが、その時点で和解するとすれば、その間にかかるコストは莫大であるだけでなく、訴訟の勝敗の行方が旗幟鮮明となり、リスクとコストを避けるための相互の互譲というダイナミズムは失われる。さらに、元来、本案審理は陪審の役目であるとともに、初期においてはフルレンジのディスカバリーを求めることによる当事者の負担を考え、主任裁判官は、特に初期のディスカバリーを、共通性を中心としたクラス認定の手続要件に関するものに制限し、本案に関するものはクラス認定の後に行うことを前提として手続を二分化して進行させる(二分化、BIFURCATION)。この時期までに被告は、事実についても法理論についても内部調査を精力的に進め、その後の見通しとして、ディスカバリーを通じて多額のコストをかけてもクラス認定を打破できる有利な証拠や法理論を探すのか、逆に、特に不利な事実が明らかになってクラス認定がなされ、被告のポジションが弱くなってしまっては、和解は不利になるので、早期のタイミングでの和解を模索するのか、という判断に迫られる。この時点までに、和解に関する方針と戦略を明確化しメリハリをつけた訴訟活動を行うことが最も重要であろう。特にWALMART事件判決以後の実務としては、原告は、クラス認定は手続要件としてだけでなく、本案に関連する重複した事実であっても、「共通性」、「支配性」の実質に踏み込んで証明する必要があるので、被告としては、クラス認定の阻止に向けて事実関係と法適用の両方についてこれを否定する訴訟活動を集中して行うことがもとめられる。プレトライアル手続においては、できる限り早く事案の全体像、強み弱みの把握を行い、クラス認定の見込みを判断し、早期に和解するか積極的に戦うかの判断を的確に行うことが、被告のリスクとコストを低減化するための必須事項であり、被告弁護士にとって最も重要なことでもある。
② クラス認定の成否と和解
クラス認定が否定されれば、訴訟は代表原告による個別訴訟の価値しかなくなるので、取り下げにより終結するのが通常であるが、クラス認定がされれば、その後の手続進行のために、認定された対象クラスの範囲と請求内容が、知れたるクラス構成員に対して通知と公告がなされ、期限を定めてクラス構成員にオプトアウトするかどうかの選択をさせなければならない。
クラス認定前に和解をする場合には、手続の進行状況によるが、プリーディング手続は終了しディスカバリーもある程度進んでいるので、事実についても争点についてもある程度お互いの強み弱みはわかっていることを前提に交渉がなされるが、それでもその時点ではクラス認定がなされるかどうかに確証はなく、相互に賭けの部分があるため、実質的な交渉を通して互譲がなされる。そして和解合意に至った場合、以下の通り2段階の手続がとられる。
ⅰ)和解の予備承認(PRELIMINARY APPROVAL)
まず、和解合意が成立した場合は、和解条件だけでなく、それによって拘束されるクラスの範囲とオプトアウトに関する手続、通知等の内容や、具体的救済を求めるためにはクラス構成員からの申請手続を要する場合(CLAIMS MADE SETTLEMENTと呼ばれる)はその手続、書式を含め、裁判所に和解のためのクラス認定を含めた和解の予備承認(PRELIMINARY APPROVAL)を原告被告の共同申請により求めることが必要である。この時点の主任裁判官の和解の見方は、クラス認定以前の和解は、和解のためのクラス認定を伴うこともあり、その後の和解よりもより慎重に、クラス認定の要件、和解の公正性、合理性、妥当性をチェックすべきであるという判例がある。
クラス認定の後になされる和解は、特にWALMART事件以後は手続要件とともにTRIALに向けて一貫した実体関係の証明が見通せることを前提としてクラス認定がなされるので、被告のポジションが極端に弱くなることは否めず、それを前提にするものの、真摯な交渉が繰り返され合意に達した以上は、和解に関連した裁判所の見方も、原告の有利に判断することは否めない。
ⅱ)和解の最終承認手続
これらの合意された和解条件がクラス構成員に通知・公告された後(この和解条件に従うかどうか、和解に基づく救済を申請するか否か、オプトアウトするかを一緒に通知・公告される場合が多い)、特にクラスのメンバーである旨の証明手続やCLAIMS MADE SETTLEMENTの場合には、所定の書面による申請状況等をクレームアドミニストレ―タ―に提出させる。そして、オプトアウトの状況、和解条件に対するクラス構成員の反応、応答率、異議や反対の状況等を見て、和解条件が実際の救済に役立つか、金額規模等に応じた原告弁護士報酬となっているか等、さまざまな観点で審査を行い、最終和解ヒアリング(FAIRNESS HEARING)がなされる。オプトアウトしなかったクラス構成員やクラス弁護士(CLASS COUNSEL)以外の関係弁護士等の関係者はヒアリングに参加して異議を申し述べることができ(OBJECTOR)、和解条件の一部変更や、しばしば高すぎる原告弁護士費用の是正がなされ、裁判所が最終的に承認(FINAL APPROVAL)して初めて、和解条件に従った救済、分配、弁護士費用の支払いがなされる。
③ 和解のみを目的としたクラスアクション(SETTLEMENT ONLY CLASS ACTION)
このような状況の中で、原告被告双方に和解を進める利害が共通する場合には、クラスアクションを開始する前に原告被告で和解協議を行い、合意が成立した時点で、クラスアクションを提起し、和解承認手続を通じて、原告の立場では救済の公定性、強制力、執行力を確保し、被告の立場では協議を通じてできるだけ有利柔軟な和解条件で合意したうえで、和解条件による責任を認める代わりに、その余の責任の全面的な免除の確認(GENERAL RELEASEと呼ばれる)を取り付け、既判力、遮断効による紛争解決の最終性・一回性を確実化しようとする。
通常の和解は、クラスアクション提起後に協議により和解に至るが、この形態は和解に向けての両当事者の意思はあらかじめ合致しており、原告被告とも上記の思惑の中でクラスアクションの手続を利用するものであるので、通常和解と区別する意味で「和解のみを目的としたクラスアクション」(以下、「和解目的クラスアクション」という。)と呼ばれる。
和解目的クラスアクションは、裁判所の監督が及ばない段階で実質合意に至り、訴訟手続を利用するものなので、上述した通り両者のパワーバランスが露骨に反映されやすく、濫用的和解(特に大規模不法行為事件などで原告弁護士が競合している場合になされる逆オークション和解がその例として指摘される)の温床になることが指摘され、未だにその有効性の議論がなされている。
(参考)AMCHEM事件連邦最高裁判決
連邦最高裁がこのような和解目的クラスアクションの有効性とその条件について初めて判示したのがAMCHEM判決である。
この事件はアスベストによる大規模不法行為事件である。原告は、被告が製造したアスベストに被曝し実際に症状がすでに発生しているグループと、症状はないが被曝したことは明確なグループ(特に将来の症状発症に対してどのような措置を認めるべきかが問題とされた)に分かれていた。控訴審である連邦第3巡回控訴裁判所の判決は、第1審がその両方の利害の違いに配慮することなく一つのクラスとして和解を認めたのは、損害の有無、因果関係等での取扱いはまちまちで支配性を欠くこと、および各州不法行為法による取扱いが異なるので集団としての訴訟を維持管理できるか(manageability:管理可能性、連邦規則23条(b)(3)(D))という観点で連邦規則23条(b)(3)の要件を欠くという理由等で、和解のクラス認定を否定した。この事件は、原告・被告は第1審が実際に開始される前に和解合意し裁判所が承認したが、上述した和解の最終認定手続の中で異議申立を行ったOBJECTORが提起したもので、OBJECTORはさらに上告した。連邦最高裁は、この事件について、和解といっても判決の場合と同様、クラス認定要件をすべて充足すべきで、和解の公平性に配慮する控訴審の姿勢は正しいとして控訴審のクラス認定否定の結論自体は支持している。しかし、当事者が判決を求めず和解承認を求めている場合には、➀クラスアクションの成立要件のうち連邦規則23条(a)に定める共通性等の要件は集団的訴訟取扱いのコアとなる要件であるが、(b)(3)の支配性・優越性(管理可能性)はいわばその付加要件としてオプトアウト型クラスアクションの審理の観点で請求に十分なまとまり(COHESIVENESS)があることを確認する意味で求めるものである。②和解の場合には判決を求める際の要件である管理可能性は必要ではない、と判示した。この判決は、クラス認定の成立要件は判決を求めることを前提とするもので、和解の承認の場合は、集団性のコアである共通性等は緩めてはならずむしろクラスの定義はより厳しい基準で画定すべきだが、管理可能性は必要ではないとすることで、成立要件のうちの支配性・優越性(管理可能性)の位置付けを明確化したといわれる。以上の通り、和解目的クラスアクションは多用されるが、初めから和解目的であるからどのような和解でも許されるということではなく、原則として判決で要求されるクラス認定要件を満たすことを基準に、その公正性、合理性、妥当性を求められることに留意すべきである。
⑶ 和解条件を巡る諸問題
① 和解の承認条件
和解の承認に当たっては、以下のような事項を特に精査して、その公正性、合理性、妥当性の判断がなされる。
・和解に至る経緯・事情
適切なディスカバリーを経て、真摯に交渉し、互譲がなされたか、和解の濫用・通謀的要素はないか、クラス構成員の利益は確保されているか
・和解の有利性
陪審審理に移行した場合の見込みと、和解することの有利性、コスト・期間の有利性、救済の柔軟性
・和解条項の性格および具体的な救済の見込み、それによる影響
少額・純粋な経済事案のように、適切な額が分配されれば終了するものか、大規模不法行為のように、人身損害、遅れてくる請求、後遺症等複雑な要因があるか。和解基金が設定されるか、申請なく分配されるものか、申請行為が必要でその手続が厳格で認定されにくいようなものか、申請の見込みが少なく、一方で和解基金の残金が被告に戻されるような偏頗な基金となっていないか。現金支払いではなく、クーポンや修理の提供で、実際には使いにくい条件になっていないか。FLUID RECOVERY,CYPRES DISTRIBUTION等の被害者の現実被害と直接関係のない救済を認める場合、適切な条件になっているか等
・他の訴訟や救済との関係
和解が他の訴訟や救済に影響を与えないか
・手続に対する反応・反対
オプトアウトが多い、OBJECTORが多い等和解手続に対する反対者が多くないか
・原告弁護士・代表原告への報酬の妥当性
クラスが実際に受け取る救済額に対して、釣り合いの取れない報酬を原告弁護士、代表原告に払おうとしていないか
② 和解条項を巡る諸問題
和解条項は事案によって異なり、一概に定式化できるものではないが、多くの和解契約は、以下のような要素で成り立っている。そのうち特に問題になりやすいものについて、コメントする。
A.前文(RECITALS)
当事者、事案の概要、両当事者の主張、クラスアクションとしての経緯、和解協議の進行、和解に至った経緯等をベースに、和解を行うことが訴訟を続けることの勝敗リスク、負担、期間、コストを考慮すると両当事者の最大利益に合致し、また、真摯に交渉を重ねた結果であるので、和解内容は公正、合理的かつ妥当であるという全般的な記述を行うのが一般的。
B.定義(DEFINITIONS)
クラスの範囲、対象期間、クラス弁護士、対象製品・サービスおよび不具合内容・損害、和解の予備承認、オプトアウト、救済申請手続、オブジェクション手続、最終ヒアリング手続、効力発生日、GENERAL RELEASE、和解救済手続申請の期間等の定義を記載する。
C.和解条件(TERMS AND CONDITIONS)
- settlement class
定義された対象製品/サービス等の不具合によって損害を受けた態様、期間を特定し、その所有者等を客観的に定義したうえで、除外されるべき対象者(すでに救済を受けたもの、被告関係者、オプトアウトする者、訴訟関与関係者等)を明確化する。
(参考) 和解クラスの定義の意味とASCERTAINABILITY、GENERAL RELEASE
b. クラス救済の内容、請求資格(class relief, eligibility)
同じ被害を受けたといっても、その時期、態様によって救済すべき内容が異なる(たとえば、製品の不具合により、修理代を支出した場合にはその返還、将来の故障に備えた無償修理期間の延長、不具合が客観的にひどい場合の特定ができる場合は交換および所定の金銭賠償等)ので、その内容とともに、それぞれの救済の内容に応じた請求資格を客観的に定める。消費者クレームについては被告がEND USERの情報を有していない場合も多く、その場合には、購入の記録・領収書、写真、修理伝票等の客観的な購入・不具合の証拠を添付して、所定のフォームで申請してもらい資格を確認する必要がある(CLAIMS MADE SETTLEMENT)。
参考:CLAIMS MADE SETTLEMENTの問題点
直販を行っている場合を除き、流通経路を経て販売等を行った消費者のクレームに関するクラスアクションについては、メーカーや卸売業者はEND USER情報を持っておらず、そのような場合はCLAIMS MADE SETTLEMENTとならざるを得ず、消費者製品・サービスについてはこの例が多い。その場合、①証拠書類を含む申請書類の偽造やなりすまし等が多く、モラルハザードが無視できないという点と、②応答率(REDEMPTION RATE)が概して非常に低いわりに原告弁護士報酬は高く、クラスアクションの意義に反するという問題がよく指摘される。① 申請を巡るモラルハザードの防止
原告側からは、救済の範囲を広げるためには、申請手続をできるだけ簡単容易にし、審査手続を簡略化することが常に主張される(このような手続なしで自動的に配分されるやり方はAUTOMATIC DISTRIBUTIONと呼ばれるが、対象者の情報が把握されていなければならず、そのような例は決して多くない)。しかし、ある程度の経済価値のある救済の場合、申請手続を簡単にすると、なりすましや偽造は跡を立たず、和解の管理のために選任される第三者の専門業者であるクレームアドミニストレーター(CLAIMS ADMINISTRATOR)はそのような請求を排除するよう努めるものの、このようなモラルハザードは避けえないことを指摘する。このような事態を防止するため、特に、購入等の記録や不具合の記録がない場合に備え、和解条項中に、証明書類がない場合、刑事罰付きの宣誓書(DECLARATION UNDER PENALTY OF PERJURY)をもってかえる場合があるが、その実効性は疑わしいといわれる。
②応答率の低さ
申請手続が実際どのくらい活用されるかという点については、実証的なデータがあまりないものの、高額の配分を受けることができる場合を除き、少額であればあるほど、通知を受けていても申請しない消費者が非常に多く、おおむね応答率は10%未満(少額の場合1%未満というデータすらある)に過ぎない。
少額被害の救済を主たる目的としてきた消費者クラスアクションの目的から見ると、多額の手続費用をかけ、裁判所を利用しながら、実際に救済される比率が極めて低く救済に役に立っておらず、他方、原告弁護士には実際に救済された額を基準とするのではなく、名目配分額(和解の経済価値)をベースに1/3程度の高額の報酬が払われる実態には、いまだに強い批判がある。また、証券クラスアクションを中心に、あまりに応答率が低い場合和解を解除できることを定める(BLOW条項)場合がある。このような実態に対しては、応答率が低くなるのは不特定多数の消費者を対象とすることから仕方なく、クラスアクション制度の問題とはいえないし、むしろ通常の制度では全く救済される機会すらないことから見れば消費者の選択により応答率が低くなっても救済の機会が与えられていること自体に意味があり、さらに、配分されない残金(和解基金がある場合)をCYPRES救済で事案と関係のあるCHARITY目的で寄付する仕組みと組み合わせれば、事業者の不当な利益を吐き出させ、公益増進だけでなく、制裁と再発防止につながるという意味で公平と正義を実現でき、クラスアクション制度の公的役割にかなうという反論がある。
c.代表原告およびクラス弁護士への報酬
代表原告に対してはその役割に対するインセンティブ報酬が支払われる。多くの場合数千ドルー1万ドル程度であれば最終ヒアリングでも反対されることは少ない。
一方、クラス弁護士への報酬は和解契約書には単純に総額が記載されるが、その額の根拠、計算方法等については、クラス弁護士の報酬が過大であるとの批判を前提に様々な議論があり、特にクーポン和解を取り入れた場合の報酬の計算方法について、CAFA(2005クラスアクション公正法)において、規制が導入されているのでその内容を含めて概要を紹介する。
伝統的に米国においては弁護士費用の敗訴者負担ルール(LOSER PAY)はとられておらず、当事者各自がその弁護士費用を負担するAMERICAN RULEといわれる原則で運用されてきた。しかし、これには多くの例外があり、クラスアクションもその例外の一つであり、和解においても被告がクラス弁護士の弁護士費用を負担する合意を行うことは一般的である。
クラスの想定請求総額(経済価値)が比較的大きい場合には、いわゆるSETTLEMENT FUND(和解の最終承認後一括支出される和解基金)が形成され、その中から、裁判所手続、通知、公告その他の共通費用とともにクラス弁護士の費用、クラス構成員への救済費用等が支払われ、残額はCYPRES救済として事案に関係のある公益目的・団体に寄付されることが多い。それ以外の場合は、和解契約書で定めた救済に従うが、基金を定めない場合も多い(想定の経済価値を合意することはありうる)。
このような場合、弁護士費用の計算根拠と方法については、伝統的にLODE STAR方式という、弁護士の時間単価×実際使った時間数×係数(弁護士の経験、複雑性や期間に応じた係数。1.1-1.3程度が多いといわれる)という方式がとられてきたが、FUNDが形成された場合はクラス弁護士の貢献努力と見て、その報酬としてPERCENTAGE方式といわれる、FUND価値×一定の割合計算(一般的には25-35%。メガケースの場合には数%から17-8%)という方式がとられる場合が多い。しかし、このFUND方式による弁護士報酬計算は実際に弁護士が働いた報酬よりしばしば過大であり、弁護士によるクラスアクションの濫用の大きな誘因材料になるとして、強い批判がなされてきた(上述のCLAIMS MADE SETTLEMENTにおける消費者救済に比べ弁護士報酬が過大であるという批判等)。特にFUND方式の場合でクーポンを救済に用いる場合には、実際に使われない部分を含めクーポンの総額を弁護士報酬の算定根拠として、実質的に大きく水増しすることが行われたので、立法的な規制が必要であるとの議論がなされた。
そこで、連邦規則やCAFAでは、クラスアクションにおける弁護士報酬はあくまで消費者が現実に受け取った救済額をベースに計算することが適切とされ、FUND-PERCENTAGE方式の場合においては、クーポンを使っている部分はそのうち実際に使われた額をベースに計算し、それ以外の部分はLODESTAR方式により計算することが原則とされるようになった。またFUND-PERCENTAGE方式による計算をチェックする目的で、LODESTAR方式で裏付けをとるという方法もとられている。
(参考)クーポン和解の実際
d.流動的損害賠償(FLUID RECOVERY)および近似的損害賠償(CYPRES DISTRIBUTION)
SETTLEMENT FUNDが設定される場合において、請求総額がFUNDの額ぎりぎりで、手続費用、弁護士報酬等を支払うと不足を生じるような場合は、PRORATAで配分することが行われることが多く、その旨が和解契約書にも記載される。
しかしながら、配分・送金等の手続コストに比して、一人当たりの請求額が少なく、配分しても意味がないような場合には、クラス構成員を特定しないで被害の原因となった製品やサービスの価格を一律に割り引く形で、事実上損害額の返還を行うことがある。例えば、タクシー料金、鉄道運賃や公共料金の取りすぎが分かった場合、被害者が知りえない場合も多く、配分手続を取らず、関係の料金を一定期間一律に引き下げる方法で事実上返還する方法(流動的損害賠償:FLUID RECOVERY)が認められる。この方法に対する最も強い批判は、真の被害者と実際の受益者が異なっており、純粋な意味では損害賠償とは言えないことにある。
また、逆に、CLAIMS MADE SETTLEMENTにおいては、OPTOUTが多いとき、OPTOUTしなくても請求を行わないとき、請求されても証拠類がないために認定されない請求が多数に上るとき等の事情で、FUNDにかなりの残額を生じる場合の処理が問題となる。その処分の方法として、クラス構成員への再配分に理由がない場合には、あらかじめ和解契約書に記載されれば被告に返還することが認められるケースもあるが、被告の不当な利益を吐き出さず、抱え込むことを認めるものとして一般的には裁判所は好まない方法といわれる。そのような場合には、問題となった損害の防止、回復等にできるだけ近い関係のある公益目的を持った団体等に寄付することが定められる。このような救済は近似的損害賠償(CYPRES DISTRIBUTION)と呼ばれ、その例は少なくない。この方法も直接の損害と関係はなく、損害の公平な回復とは言えず、むしろ被告の制裁や再発防止を主眼とするもので、クラスアクションの本質を変質させるものとの批判がある。
(参考)CYPRES法理とは
元来、公益目的の信託財産が事情により当初の信託目的に使えなくなったような場合、設定された信託目的にもっとも近い目的に使う( Cy Pres Comma possibleとはフランス語で as near as possibleの意味)ことができるという、EQUITY上の法理を、特にクラスアクションに応用したものといわれる。つまり、残額を損害賠償として配分することが難しいか適当でないときは、その額を“NEXT BEST”な目的、方法で寄付し、間接的にクラスの利益になるようにしようというものである。具体例としては、クレジットカード情報が消費者保護法令に違反して管理が十分になされず、その結果、1億人以上の秘密の支払情報がハッカ―に窃取されたとして、被告管理会社に対してクラスアクションによって損害賠償を求めたが、和解に至り、被告は支払のために百万ドルのFUNDを設け請求を受け付けたが、これに応じたクラス構成員はわずか11人、その総額は2,000ドルに満たなかったケースで、残額はすべてこのようなクレジット支払のシステムセキュリティに詳しく消費者のプライバシーの保護のための非営利団体に寄付することとなった例がある。米国においては、救済方法は実質を重んじ柔軟な方法をとるといわれているが、特にクラスアクションにおいては、わが国では損害賠償の基本にある損害の回復、公平な分配だけではなく、被告の不当利益の吐き出しを通じて、被告への制裁、被害の再発防止、ひいては公益目的への寄与をも目的としているといえる。
7.和解と経営判断―企業存立にかかわる事態を避けるために
上述した通り、米国におけるクラスアクションに巻き込まれてしまった場合でも、普段から必要な体制を整備し、情報収集を怠らず、また良い証拠となるべきものを適切に残し、(秘匿特権を活用する等して)不利になりうる証拠を不用意に残さずに、特に初動の判断を誤らず、適切な戦略を立てれば、予想できない企業存立事態に至ることはまれであるといえよう。
しかし、事案によっては、訴訟の方針、特に最終的に和解すべきか、いつ、どういう形で和解すべきかについて、慎重な経営判断が必要な場合がありうる。
和解すべきかどうかは、訴訟提起前でもできるだけ早い時期に複数の練達の弁護士を確保したうえで自社の強み弱みを相手方より早く確実に把握して、実質的なディスカバリーが始まる前に、攻撃防御戦略を明確化して、タイミングを含めて和解するかどうか慎重に判断する必要がある。この判断はまさに経営判断であり、そのためには、今後の訴訟の見通し、そのチャンス、リスクとコストと和解することのメリット、デメリットについて、特に重要な案件等では、担当弁護士だけでなく、利害関係のない中立的な専門弁護士のセカンドオピニオンを取得する等タイミングを含めて和解を行うことが最も会社の利益に合致することを確認すべきであろう。一般に、巨額の和解を行えばその情報は多くの原告弁護士の知るところになり、「くみしやすい会社」、「すぐに支払う会社」との評判の下に、雨後の筍のごとく、同様の製品やサービスについて、同様の訴訟が必ず起きる(いわゆるCOPYCAT訴訟:同じような製品・サービスを提供する他の会社、業界にも波及する)ことは覚悟しなければならず、相当長期間にわたり事後処理にコスト、労力がかかることを含めて、対応を考えておく必要があろう。
しかし、それでも、見通しや戦略なく、ただ勝訴にこだわり、和解のチャンスを逃し、米国訴訟のために経営をリスクにさらすギャンブルを行うことは許されず、経営陣にはその重要性をきちんと理解させておくべきであろう。
V. 新法によるわが国制度の概要と実務上の問題点
- 新法制定の背景
新制度は「日本版クラスアクション」とも呼ばれ、消費者の少額で多数・拡散的な集団的被害を救済するため、民事訴訟法の特例として制定施行されたものである。事業者の行為によって多数の消費者に共通した少額の財産的被害が生じているとき、個別訴訟はもとより、個人単位を前提とするために共同訴訟や選定当事者制度を使っても、消費者が提訴することは、事業者との情報格差、手間や費用を考えると困難であることが長く指摘されてきた。そこで、米、仏、ブラジル等諸外国の立法例の長所・短所を参考にしながら、さまざまな議論を経て、わが国独自の団体訴訟制度が考案され、2013年12月に新法が成立した。
新法は2016年10月から施行されており、施行日以降に締結した消費者契約に関し、認定された特定適格消費者団体(以下、「特定団体」という)に限り、新法が定める集団的訴訟を提起できることになったが、本報告書作成時点では実際に提起された例は1例もない。
2.新法の特徴
新法の特徴としては、以下の点が指摘される。
- 二段階型手続
新法の最大の特徴は、二段階手続にあるといわれる。
すなわち、まず、第一段階として、原告となる特定団体は、対象消費者からの授権を受けることなく自らの判断、負担、責任において、事業者に対して対象消費者に金銭賠償を行うべき「共通義務」があることを確認する「共通義務確認の訴え」を提起することができる。「共通義務」の存在が確定勝訴判決、裁判上の和解または認諾により確認された場合には、特定団体はその申立てにより、第二段階として破産手続における債権届出手続に類似した、簡易確定手続を開始する。そして、第一段階で確認された共通義務の存在(債権届出をした対象消費者に対して既判力が及ぶ)を前提に、対象消費者にその内容を通知・公告するとともに、簡易確定手続への加入と特定団体への手続授権を促す。対象消費者は、特定団体に対して包括的な授権を行うことにより、個別の債権の届出、審理・確定・取立・配分までをすべて代行してもらい、異議申立てがなされなければ、個別の債権は確定し、迅速に救済を受けるというものである。
これにより、対象消費者からみれば、第一段階の「共通義務確認訴訟」では訴訟への関与や負担は一切なく、第二段階の「簡易確定手続」で、非常に安価なコスト(1件1,000円)で包括的に授権するだけで、訴訟費用・特定団体への報酬等を差し引いた相当の損害賠償金(原則として事業者から回収した額の1/2以上)を受取れるというものである。対象消費者は、自ら訴訟提起または参加する場合に比べ、きわめて少ない負担で簡易迅速な救済が受けうる。
⑵ 原告適格が限定されていること
米国クラスアクション濫用の原因の一つとして、原告適格を制限せず、誰でも提起できることとしたことから、原告代理人が自らの利益のために訴訟に実質的に関与し、その専横を許したことが指摘されてきた。このため、新制度では、すでに消費者契約法(13条)に基づき認定を受けて差止請求関係業務を行っている「適格消費者団体」の中から、被害回復関係業務に適格性があるとして内閣総理大臣が認定監督する特定団体だけに、原告適格を与えた。そして、訴訟事務だけでなく情報収集、消費者等への情報提供、金銭管理等の被害回復関係業務を適切に行わせ、また、濫訴を禁止するとともに、対象消費者に対する善管注意義務を負わせ、制度の健全な運用の確保を図っている。なお、現時点では、認定されている特定団体は3団体に過ぎない。
このように原告適格は制限され、消費者自身も共通義務確認訴訟を提起したり、補助参加したりすることもできないこととされる。
⑶ オプトイン型であること
クラスアクションでは、最低一人の代表原告がクラスメンバー(他の多くの被害者)の意向を確認する必要なく、いわば、訴訟を勝手に始めることが認められ、クラス認定後は正式にクラスメンバーを代表し、その結果は有利にも不利にも、積極的にオプトアウト(訴訟手続からの離脱)しないクラスメンバーを拘束するので、オプトアウト型といわれる。
これに対して、新法は、第一段階の結果が、確定勝訴等対象消費者にいかに有利な結果であっても、第二段階の簡易確定手続にオプトイン(加入、授権)しなければ、対象消費者にその効力は及ばないという意味で、オプトイン型と呼ばれる。
特定団体が確定敗訴した場合には、簡易確定手続はそもそも始まらず、共通義務確認訴訟の費用は対象消費者から回収できず特定団体の負担となるので、特定団体は訴訟提起事案の選択を慎重に行わなければならない。また、特定団体が確定敗訴する場合には、対象消費者はその後別訴で個別に争っても敗訴する可能性が高いので、特定団体は濫訴の防止と対象消費者の利益保護の意味でも、対象事案の選択・訴訟遂行に高い注意義務を負うものとされる。
⑷ 対象案件が消費者契約に起因しているものに限られること
新法は対象案件を、事業者(法人、社団・財団・公共団体、事業を行う個人を含む)と消費者契約(労働契約を除く)を「直接締結」した対象消費者(消費者契約法に定める定義と同様、事業を行う場合におけるものを除く個人をいう)に対する金銭支払義務を前提とした。
ただし、「直接締結」には注意すべき点がある。まず、新法3条3項2号により、不法行為に基づく損害賠償請求との関係では、直接の契約当事者でなくても、当該契約当事者の債務の履行をする事業者は被告となりうる。また、消費者契約の締結を勧誘し、勧誘させ、または勧誘を助長する事業者も被告となりうる。被害の原因となった契約に直接関与し、影響力を与えたことが、不法行為に当たる場合には、被告適格が拡張され、被告となりうるのである。これらは、例えば、請負契約における下請事業者、保険勧誘を行った保険代理店、不動産仲介業者、マルチ商法を勧誘させる統括業者、価値のない自社株式(非上場等)が多数の消費者に高額で販売されることを知りながら販売業者に自社株を販売した者等をいうとされる。テレビコマーシャル等により一般大衆に対して広告宣伝を行ったに過ぎないマスコミや、小売店に単に販売したに過ぎないメーカー等は、勧誘方法を具体的に指導したり、必要な人員・物品を提供したりするなど、勧誘行為に直接的、実質的に関与する行為をしていなければ、「勧誘を助長する」には当たらないとされる。
⑸ 対象事案が定型的な請求に限定されていること
①契約上の債務の履行請求
例えば、敷金返還請求、保険金返還請求、ゴルフ会員権契約の預託金返還請求等である。なお、物品の引渡、修理請求等の金銭債務でないものは対象外である。
②不当利得に係る請求
例えば、民法、消費者契約法、特定商取引法その他の特別法により契約が無効、取消、解除、クーリングオフとなった場合の不当利得返還請求権。具体的には、悪質商法被害で無効・取消となった場合の代金返還、入学しなかった大学からの学納金(授業料)の返還、結婚式場の利用契約を解除した際に支払った高額な違約金の一部返還等である。
③契約上の債務の不履行による損害賠償請求
例えば、債務不履行の場合の填補賠償、付随義務違反の損害賠償等。
④瑕疵担保責任による損害賠償請求
例えば、商品に瑕疵、不具合、仕様不一致、法令違反等がある場合の損害賠償。具体的には、自動車や電気製品に隠れた瑕疵が集団的に生じていた場合や、耐震基準に違反したマンションについての損害賠償等である。なお、改正民法施行により瑕疵担保責任規定は削除される予定であるが、そうなれば③の契約上の債務不履行に含まれることとなる。
⑤不法行為に基づく損害賠償請求
例えば、価値のないものを高額な商品であるかのように信じ込ませる悪質商法の場合の損害賠償等である。
民法以外の特別法によって生じる不法行為損害賠償請求権は対象外であり、特別法に定める証明責任の転換、損害額の推定規定等も適用されない。具体的には、金融商品取引法、保険業法、独禁法、特許法、製造物責任法等に基づく損害賠償請求権は対象外であり、特別法による推定、立証責任転換規定等は適用されない。
⑹ 除外される損害があること
上記の定型的な請求に当たっても、第二段階である簡易確定手続になじまない、類型的に定型性(支配性)を欠く損害はあらかじめ除外されている。具体的には、拡大損害、逸失利益、生命・身体・精神的損害は対象外とされている(新法3条2項)。その結果、新法による損害賠償の範囲はおおむね消費者契約の対価およびその遅延損害までである。このため、事業者は係争利益(最大敗訴額)を、次のように予測できる。
⑺ 「共通義務」という考え方と要件
共通義務確認訴訟で確認の対象となる共通義務とは、「消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、事業者が、これらの消費者に対し、これらの消費者に共通する事実上及び法律上の原因に基づき、個々の消費者の事情によりその金銭の支払請求に理由がない場合を除いて、金銭を支払う義務」とされる(新法2条4号)。共通義務確認訴訟では、個々の消費者の請求権自体ではなく、第二段階の簡易確定手続で確定される請求権の基礎となるべき「相手方事業者が対象消費者に対して負うべき共通的、抽象的な金銭支払義務」「対象消費者と事業者の概括的な法律関係」があるかどうかがまず確認されることとなる。最終的には本案の問題として事業者が消費者に対して賠償義務を負うのかどうか(損害の発生や原因と損害との因果関係を含む)を、立証責任の配分に基づき、基本的に原告が立証する必要があるが、その前提として、以下の訴訟要件のすべてを満たす必要がある。
- 事業者の消費者に対する金銭支払義務に関する法律上および事実上の原因が共通であること(共通性)
- 簡易確定手続に移行しても個別の債権確定に相当の審理をする必要がない程度に集団として、まとまりがあること(支配性)
- 相当多数の対象消費者がいること(多数性)
これらを満たすイメージ例として、大学の学納金が挙げられる。入学試験に合格しながら4月1日以前に入学辞退した場合、入学金だけでなく、初年度の授業料も返還しないこととする契約条項は、授業料の部分について、消費者契約法上無効とされている。大学が複数の辞退者に授業料を返還しないという同一の行為(事実上の原因が共通)により、当該契約条項が無効であることに基づき共通して授業料を不当利得として返還すべき義務が生じている(法律上の原因が共通)ので、共通性を満たす。さらに、授業料を返還しないという契約条項が無効である以上、基本的にはすべての辞退者が返還を受けられるはずであり、既に返還済みである等の例外的な場合にのみこれが認められないに過ぎないため、簡易確定手続での書面審理に相当の困難があるとはいえず、支配性を満たす。そして、このような共通性、支配性を満たす辞退者が相当多数いる場合には、多数性を満たすこととなる。以下では、構成要素ごとに詳しく見てみよう。
⑻ 共通性
集団的に救済を図る以上、被害の原因が共通していることは必須である。消費者庁の一問一答では「相手方事業者の対象消費者に対する個々の金銭支払義務を基礎づける事実関係がその主要部分において共通であり、かつ、その基本的な法的根拠が共通であること」が必要であるとしている。
例えば、化粧品に異物が混入していることが判明し、集団的に代金返還を求めるなら、各消費者の持つ対象物に異物が混入したという事実上の原因がまず共通している必要がある。別の言い方をすれば、ある集団をとればすべての製品に異物が入っていることが立証される必要がある。しかも、それによって化粧品が期待された品質を欠くか、有害であるため(瑕疵担保責任または債務不履行)、代金相当の損害賠償または解除による不当利得返還請求ができるという、法律上の根拠が共通である必要がある。
なお、クラスアクションにおける共通性と異なり、共通義務確認訴訟における共通性は、原因において共通であればよく、必ずしも因果関係や損害は共通しなくてもよいとされる。その理由は、損害や因果関係、時効、弁済等、個々の消費者に固有の事情は簡易確定手続で審理されるので、必ずしも共通である必要はないと説明される。ただし、第一段階においても、損害や因果関係等、対象消費者に対して金銭を支払うべき義務の発生原因を欠く場合には、本案の判断として棄却される可能性もあるので、被告側の立証活動は訴訟要件だけでなく本案自体についても十分に行うべきであろう。
⑼ 支配性
支配性とは「共通争点が個別の争点に対して支配的である」ことといわれる。新法3条4項では、共通性や多数性を満たす請求であっても「事案の性質、簡易確定手続において予想される主張および立証の内容その他の事情を考慮して、・・対象債権の存否および内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるときは、裁判所は共通義務訴訟の全部または一部を却下しなければならない」とされている。支配性とはそのような事情がないことをいう。
原因が共通していても、第二段階の簡易確定手続で消費者ごとに損害や因果関係等を判断しようとすると、個々に事情や争点が異なり「相当程度の審理を必要とする」場合には、簡易迅速な判断が困難となるため、支配性がないとして却下しなければならないと定められている。
具体例を挙げれば次のとおりである。
瑕疵が特定製品のすべてに想定されるとしても、実際の不具合出現にはばらつきがあり、個々の製品ごとに判定しなければならない場合や、違法な勧誘はあったが、消費者の購入動機がそのような勧誘に直接起因したのかという因果関係や、過失相殺を考慮する必要があり、個々の判断が必要な場合等、がこれに当たるとされる。
簡易確定手続では原則として個別の債権の証拠調べは書証に限定され(新法45条)、証人・当事者尋問や検証・鑑定はできない。当事者の陳述書も書証になるとされるが、すべて陳述書で立証することは現実的に困難であり、基礎となる書証は実務的には必要であろう。被告としては、このような書証がない場合、または、書証はあっても因果関係や損害発生の審理を行うために書証以外の証拠調べが必要である場合には、支配性を満たさないと主張、反証することが考えられる。
⑽ 多数性
(共通性、支配性を満たす)財産的被害が相当多数の消費者に生じている場合をいう。個別の訴訟を行うよりもこの制度によるほうが効率がよい程度の人数が必要であるとされ、おおむね数十人程度であるとされる。このため、製品の不具合によって共通義務確認訴訟が提起されたが、リコールを行って大多数不具合は修復され、残った人数が少ない場合には、多数性の要件を満たさないとして却下されることがありうる。
⑾ 片面的既判力しか生じないこと
新法では、特定団体が共通義務確認訴訟で確定勝訴(裁判上の和解、認諾を含む)した場合と、確定敗訴した場合とで、既判力が及ぶ範囲が異なる、片面的既判力と呼ばれる問題が生じる。すなわち、確定勝訴の場合には、その効力(既判力)は他の特定団体にも第二段階に加入する対象消費者にも拡張される。しかし、確定敗訴の場合の効力は、他の特定団体には及ぶが、対象消費者が債権届出を行う第二段階手続は開始されないため、対象消費者を拘束することはできない。
これを事業者から見ると、第一段階で確定敗訴・和解すると、第二段階では共通義務の(不)存在について蒸し返しはできず、防御できる範囲は共通義務を前提とした対象消費者の個々の事情に限られる。たとえば、個々の消費者によって、損害や因果関係が異なっている、過失相殺できる要素がある、弁済した、時効が完成している、等である。ところが、事業者が確定勝訴した場合は、他の特定団体も蒸し返しはできないが、対象消費者は、その利益を実質的に代表する特定団体が確定敗訴しているのにもかかわらず、上記の通り拘束を受けず、蒸し返しが可能となる。
このような不公平は武器平等を原則とする民事訴訟においては極めて例外的であるといわれる。このような片面的既判力の発生は新制度の制度設計上やむを得ないものであるが、対象債権を契約類型に限定し拡大損害等をあらかじめ除外した理由も、事業者に予測可能性(最大敗訴額は予測できる)を持たせ、一回の係争で十分攻撃防御を尽くさせることで、事業者の片面的な不利益を緩和しようとしたものであると説明されている。(つづく)