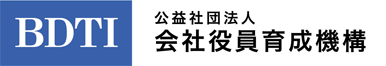本号からお読み頂く方のために。BDTIは、日米のクラスアクションを比較し、日本企業が取り組むべきリスク管理を考えるセミナーを2017年1月に実施した。多くの有意義な提言がなされたが、同時にクラスアクションを研究する場の必要性も認識された。こうして始まったのが、本研究会であり、研究成果をまとめたのが本報告書である。
Ⅰ. 本研究会の目的
Ⅱ. 本研究報告書の利用上の注意と構成
Ⅲ. 日米クラスアクション制度の俯瞰
Ⅳ. 米国クラスアクション制度の概要と実務上の問題
1. 国におけるクラスアクションとは
2. 米国におけるクラスアクションの動向
3. クラスアクション手続の概要
4. クラスアクションにおける証拠開示手続をめぐる問題(以下本号)
5. クラスアクションの防御戦略(以上本号)
6. クラスアクションの和解戦略
7. 和解と経営判断-企業存続にかかわる事態を避けるために
Ⅴ. 新法によるわが国制度の概要と実務上の問題点
1. 新法制度の背景
2. 新法の特徴
3. 新法による手続の流れ
4. 特定適格消費者団体
5. 新法のリスクと対象事案のイメージ
6. 考えられる対策
本号がカバーする部分の監修者2人を、BDTIから紹介する。
服部有紀弁護士 ホワイト&ケース法律事務所アソシエイト
https://www.whitecase.com/ja/people/yuki-hattori
総合電機メーカー法務部に所属して、アメリカにおけるクラスアクションに法務部員として関与した経験を有する。訴訟代理人としての視点だけでなく、社内の視点を有することの意味合いは大きい。クラスアクション遂行では、裁判所における訴訟活動もさることながら、社内意思決定のために要する時間と労力が甚大である。取締役会が意思決定するのに必要な情報は何か、正確な情報をどう提供するか、経験から知っている服部氏は、研究会にとって貴重であった。
高取芳宏弁護士 オリック東京法律事務所パートナー
http://orrick.jp/JP/Lawyers/Yoshihiro-Takatori/Pages/default.aspx
日本に設立予定の国際紛争解決センター及び京都国際調停センターの立ち上げに尽力している、国際紛争解決の第一人者である。このため、外資系企業のみならず国境を超えたビジネスを展開する日本企業がクロスボーダーで大規模なビジネスを展開する際には、必須相談スポットになっている。現在立法化の動きもあるが、日本には弁護士依頼者間秘匿特権がないため、国境をまたがる法的手続では思わぬ落とし穴となることがある。この落とし穴を知り、本当に必要な護身術を伝授する高取氏は、研究会の大きな頼りとなった。
前号からの続き(第1号はこちら)
報告書本文
4.クラスアクションにおける証拠開示手続きをめぐる問題点
⑵ 訴訟提起後の開示手続の概要
➀ディスカバリー手続の概要
一般的にディスカバリー手続は、以下の順序で行われることが多い。
また、以下のディスカバリー手続は、人身等に関する検査を除き、裁判所の関与や許可なく、当事者が主体的に進めることが求められ、当事者間で見解が対立してもできるだけ協議に基づき自主的に解決することが期待される。したがって、真に裁判所が判断すべき紛議が発生した場合を除き、双方の代理人としても裁判所に解決能力がないとみられ、裁判所の印象を悪くしたくないという相互心理が働くので、代理人の相手方代理人に対する説得力の有無の点で、その経験と実力が示される場面でもある。ディスカバリー対策の戦略性や対応力の有無は弁護士管理・評価の点でもきわめて重要である。
ⅰ)DISCOVERY PLAN(ディスカバリー計画)
以下のディスカバリーを、どういう順序で、いつまでに、どのように行うかを当事者で協議し、裁判所における確認を行う。最初のスケジュールコンファレンスにおいて、他の手続とともに確認され、裁判所からディスカバリーオーダーが出されることになるので、ディスカバリー計画の策定のために、できるだけ早期に経験ある弁護士とともに十分な準備を行うことが必要である。
ⅱ)INITIAL DISCOVERY(最初に行われるディスカバリー)
ディスカバリーの重複や無駄な負担を避けるために行われるもので、相手方の要求を待たず、最初のスケジュールコンファレンスから原則として14日以内に開示すべき義務がある。その内容は、証人、提出予定の証拠、損害賠償を求める場合の明細・資料、賠償責任保険の内容等である。
ⅲ)INTERROGATORIES(文書による質問書)
当事者同士で訴訟に関連する質問を書面で行うもので、連邦規則では原則として各当事者あたり25問までに制限される。質問を受けた当事者は原則として30日以内に回答する義務がある。
ⅳ) DISCLOSURE (REQUEST FOR DOCUMENT PRODUCTION:文書提出要求、INSPECTION:検証要求)
文書提出要求は、相手方または第三者(第三者に強制する場合にはサピーナによる命令が必要)に対して証拠の入手のために文書等の提出を求めるもので、米国訴訟で最も手間とコストがかかり、訴訟の行方に影響を与える、強力な手段である。対象はLITIGATION HOLDで求められるとおり、訴訟に関連性があり、会社が所持またはコントロールする情報(親会社の業務について子会社が所有する情報、従業員が保持するもの等を含む)であって、秘匿特権等の保護を主張できるものを除き、媒体、保存場所および形態を問わず(たとえば会社の保存書類、グラフ、表、写真、電子データ、EMAILは言うまでもなく、個人のメモ、電話の録音等、業務に関係するあらゆるものを含む)、広範囲に及ぶ。また、電子データについては、内容だけでなくその属性や作成・変更・削除の履歴を示すメタデータを含む。
なお、電子データについては、e-DISCOVERYとして、情報の種類、提出形式による取り扱い、過度な負担の回避のための取決め、秘匿特権等の保護のための手続、CHAIN OF CUSTODYを確保するための作業手順(対象情報の特定、データ収集・保全、データ処理、分析、証拠閲覧、提出書類の作成、翻訳等)の確認等、より複雑な手続がある。
ⅴ) REQUEST FOR ADMISSION(自白・事実承認要求)
特に、争いのない事実について確認を求めるものである。このことにより、真に対立のある事実を絞り込むこととなる。
ⅵ) DEPOSITION(証言録取)
証言録取とは、ディスカバリーの一環として、当事者相互の情報収集を目的として、相互に陪審審理で証人となり得る者の証言を録取するものである。
日本の証拠調べ手続は、立証事項に関する事実認定および争点に対する裁判官の心証形成を目的として裁判官の面前でかつ原則として公開の法廷でなされるのに対して、米国ではディスカバリーの一環とするため、他の手続と同様、裁判所が関与することなく、当事者および速記官だけで(速記録だけでなく、ビデオの録取も併用される)なされることが通例である。米国内であれば多くの場合、弁護士事務所やホテル等の任意の場所において、連邦規則等に定める範囲内で、進め方も代理人同士の合意に基づきなされる。連邦規則によれば、米国内であれば原則として各当事者10名(1人1日7時間以内)までしか行えないが、大型事件等では裁判所の許可があれば、原告代理人から被告の関係者(企業全体のことを知っているべきであるとされる、ないしは知りうる立場にある企業代表者(連邦規則30条(b)6に定められる証人であることから、30(b)6証人といわれる)および他の手続で特定される個別関係者)としてこれを超える指名がなされる場合もありうる。
証言録取の実態は、わが国の手続における反対尋問に近く、文書提出手続で収集したEMAILや書類等を証人に示して、証人の証言の矛盾をついてできるだけ質問する側に有利な情報としてその主張の正当性を印象付け、速記録やビデオに記録し、陪審審理で開示して質問する側に有利な心証を形成させたり(証言録取で指摘されたことに対して、陪審審理で矛盾するような供述はしにくいことに加え、証人が感情的になったり、困った表情を示したりすると、陪審の印象としては、証人は信用できないという印象を持つ)、他の反対の証言の弾劾に利用したりする等、訴訟の行方を左右する重要性の高い手続である。米国訴訟に慣れない日本人証人にとっては、最も負担の大きい手続であり、経験豊富な米国弁護士の指導に基づき周到な準備を行うことが必要である。
なお、日本人の証人に対する証言録取は、できる限り、日本国内(米国司法権の及ぶ大使館内または領事館内であることが必要)で行うことが準備やコストの面だけでなく、証人の精神的な負担の面でも望ましい。
(参考1)証言録取に対応するためのDOs & DON’Ts(例)
日本企業、日本人証人に対する米国弁護士のアドバイスにはさまざまなものがあるが、以下はそのごく一部である。
〇 DOs
・証言録取の前に十分な準備時間をとり、証言のルール、弁護士のアドバイスをよく理解し、自らに関係する関係書類を熟読してその意味について記憶を呼び戻し、さまざまな質問に対して証言がぶれないよう準備する。30(b)6証人は会社のことを知っている代表者として取り扱われるので、知らない事項でも予想される質問に対して幅広に準備する。
・質問を注意深く聞き、示された書類等は知っているものでも十分に最後まで読み返し、時間を十分とって、よく考えて答える。
・質問の意図が分からない、どう答えるかわからない場合、質問を聞きかえし、質問の意図を正確に理解して答える。
・聞かれたことだけに、正確に、できるだけ短く答える。
・正直に事実だけを答える。
・質問に関して知らない、わからない場合、推測で答えず、必ず質問を完全に理解してから答える。知らないこと、わからないことはそのとおり答える。
・どんな質問に対しても表情を変えず、かつ、丁寧に答える。
・仮定的、断定的な質問には、前提に同意できないので答えられないと回答する。
・被告側弁護士は証言についてアドバイスできる場合がある(OBJECTION:質問が不明確・広範、繰り返し、仮定的、断定的、高圧的、秘匿特権に係る場合等の異議)。そのために、質問が終わってもただちに答えず、若干の時間をおいて弁護士にOBJECTIONの機会を与える。被告弁護士の発言は、混乱した証言の助け船のアドバイスである場合もあり、異議の申し立てがあれば、弁護士の指示があるまで答えず、時間をとって臨機に考え直す。そのまま進めてよい場合には弁護士は“YOU MAY ANSWER”(答えてよい)とアドバイスするのが通例。また、特に通訳をはさんだ証言録取の場合には、仮に英語で意味がある程度わかっても、即答せず、きちんと翻訳されるのを待って、一呼吸おき、意味を確認、理解しながら証言することも重要である。通訳による誤訳を防ぎ、その間に、弁護士が異議を言うチャンスも増える。
〇 DON’Ts
・証人は事実以外の自らの考えを主張・説明をし、説得しようとしてはいけない(証人にとっては、聞かれたことしか答えられず、十分に説明できなかったと不満が残るくらいが、相手方にとっては情報をとれなかったこととなり、証言録取としては通常成功といわれる)。
・決して感情的になったり、怒ったりしてはいけない。
・早く終わらせようとしてイライラしたり、高圧的な態度をとったりしてはいけない
・質問を遮ったり、質問が終わらないうちに答えたりしてはいけない(質問を想定して答えることとなり、混乱した答えになり、相手方弁護士に付け込まれる。また、質問と答えが重複すると速記者が記録に困ることとなる)。
・相手方弁護士と議論する場ではない。反論しない。
・聞かれていないことには絶対に答えない。知らないことを推測したり、質問の意図を先回りして敷衍したり、自発的に補足したり、解説してはいけない。相手方弁護士に教えようとしてはいけない。
・困った、怯えた表情を見せたり、相手方弁護士の質問をかわそうとして妥協したりしてはいけない。事実と記憶に基づき一貫した姿勢を変えない。
・絶対にごまかしたり、うそを言ったりしてはいけない。後で不一致を攻撃され致命的になる。
・英語が話せても英語で答えず、必ず通訳を介して日本語で答える(正確性と考える時間の確保)。通訳が終わる前に回答を始めてはいけない。
ⅶ)EXPERT WITNESS(専門家証人)
わが国の手続においては、鑑定人は裁判官の判断の補充として、当事者の申立てにより裁判所から命じられて専門的立場から意見を述べるのに対して、米国訴訟においては、ディスカバリーの一部としてさまざまな事項について原告・被告双方から自らの主張に沿った専門的意見として専門家証人が頻繁に活用される。専門家証人には証人適格が必要であり、科学・技術、法律、マーケティング等の専門知識、経験、教育経歴について客観的に確認できる専門性(FAKE SCIENTIST、FAKE EXPERTではない)があり、事案に関する知見の裏付けの有無や信頼性について、弾劾される可能性があるので、弁護士を通じて適切な専門家証人を確保しておく必要がある。特に専門家証人について、その科学・技術または法的な理論が本当に事案に関係しており、十分な信頼性があるかどうか具体的な根拠を求める連邦最高裁判決(DAUBERT事件判決。このような手続はDAUBERT HEARINGと呼ばれる)がなされて以降、単なる専門家では適格性としては足らず、実質的な専門性や経験が確認され、時として争われることが一般的となっている。
②ディスカバリーを有効に活用し、防御するための準備と戦略の必要性
ディスカバリーは上記の通り、当事者双方とも、事案に関連するあらゆる情報について、非常に短期間で大量の関連情報について、誠実に開示を行うことで、訴訟における武器平等を実現するとともに、事案の解明を当事者が自主的に行う手続である。このような手続に慣れていない企業で、平時からの準備がまったくない結果、訴訟提起によって大混乱し、不必要な証拠開示をしてしまったり、秘匿特権を放棄する開示をしたり、正当な理由のない破棄や隠ぺい等により必要な開示をせず、厳しい制裁を受ける等、戦わずして自滅しているといわれる例も少なくないといわれる。
このような観点で、クラスアクションに巻き込まれる恐れのある日本企業が注意すべき準備事項の一例をあげると以下のとおりであろう。
ⅰ)平 時
・経営陣から、各部門、グループ会社に至るまで、米国訴訟の提起を想定した準備事項の確認とTO DO LISTの整備、監査手続等での確認、経験ある弁護士、ディスカバリーベンダー、専門家のリストアップ
・リスクアプローチに基づき、米国訴訟がどの部門のどういう問題で起きやすいか、いったん訴訟になれば、どのような情報がディスカバリーの対象になるかを想定しながら、文書保管、EMAILその他の電子データの取り扱いを定める書類保存規程等を整備・改善し、監査等で実施状況を確認する。
・マネジメント層、関係部門、関係者に対する米国訴訟に関する教育を行う。特に書類・EMAILの作成、保管、変更、改竄、廃棄に関する教育は重要。
(参考2):ディスカバリーのイメージ
日本企業にとって、米国の訴訟でeディスカバリーや証言録取がいかに負担になるかは経験のない会社にとっては想像しがたいものであるが、特に社内文書が決め手になることがあり、簡単な架空事例でそのイメージを示すと以下のとおりとなる。
- たとえば、日本で設計し、米国で製造販売されていた精密機器が頻繁に壊れるクレームが寄せられた事例
・簡単に壊れるというクレームが米国サービス会社に相当数寄せられていた。
・米国製造販売会社はクレームデータの統計とともに、実際に起こった不具合を日本の設計部門に連絡し対策を要求したが、対応してくれないので、米国担当者は憤激のあまり、「史上最低の製品」「設計ミス」「リコールしなければ市場から撤退しなければならない」というメールを日本の幹部宛に送っていたことが後のディスカバリーで判明した。
・米国原告弁護士は消費者クレームを普段からWEB等で収集しているが、本訴訟のきっかけは、複数のユーザーから原告弁護士に本件の情報提供がなされたことによる。原告弁護士は単価が比較的高く、販売台数が10万台と多いことに目をつけ、完全成功報酬制度を活用すれば、訴訟の経済的利益の1/3程度の巨額の弁護士報酬が稼げると予期して(全数リコール救済になれば、一台当たりの販売額10万円×10万台×1/3=34億円が最大額となる)、WEBで同様のクレームがないか情報提供を求めたところ消費者からいくつか情報が寄せられた。原告弁護士はクラスアクションとして成立することを確信し、一人の典型的な消費者を代表原告として、原告に有利な訴訟地として有名な訴訟地でクラスアクションを提起した。請求内容は、製品の品質保証違反、消費者保護法違反、消費者詐欺(壊れやすい設計であることをあらかじめわかっているのに販売し、またはクレームでわかったのにリコールせず販売し続けたことは消費者詐欺行為に当たる)という理由で、支出済の修理・交換費用の返還、対象製品の販売額の全額返還(100億円相当)および懲罰賠償を求めるもので、米国において製造販売子会社だけでなく日本の親会社に対してもクラスアクションを提起した。
・親会社は訴状の送達、管轄を争い、親会社を除外することを求めたが、設計は親会社において行っており、さらに米国の製造販売子会社を実質的にコントロールしているとの理由で、認められなかった。
・日米の両方において、ディスカバリーが始まった。その範囲は広範で、製品の商品企画、設計、発売決定、製造、出荷、広告宣伝、修理サービス、クレームデータ他一切の関係書類、EMAILの提出と、日米の会社の社長を含む幹部、関係部門、特に設計・製造・販売・サービス関係者の証言録取を要求された。
・ディスカバリーに応じて多数の関係書類(書類で3万枚相当)・データ(サーバー、PC100台分)・EMAIL(2万通分)を開示したところ、設計部門に何回か改善要求がなされており、「最低の製品」等のひどい指摘が社内でされていたことが判明した。さらに、製品起因による火災が疑われる事例があったにもかかわらず、リコールコストは高いので見送り、また、不具合が設計基準を超える非常に暑い地域でおき、しかもひどいほこりや傷、部品欠落など誤使用の形跡が見られたので、仕様条件違反の疑いがあるとの理由でリコールを含む対策をしていなかったことが判明した。また、特段の対策を行わず、漫然と販売を続けたことも明らかとなった。
・証言録取でも設計関係者はその関係書類を突きつけられ、認めざるを得なかった。
・陪審審理で争うと実損だけでなく懲罰賠償を含め数十億円レベルの賠償請求が認められる可能性があるとの弁護士のアドバイスもあり、陪審の予測不能な評決を避けるため、原告に原告側弁護士費用を含む20億円相当の和解金を支払って和解せざるを得なかった。それ以外にディスカバリーコストは2億円、被告側弁護士費用は2億円かかった。
(参考3)訴訟の勝敗を決める社内文書ーHOT DOCUMENT
・(参考2)のような事例で、実際、陪審裁判で懲罰的賠償が認められたケースとして以下の事例があり、訴訟の決め手になる書類(「HOT DOCUMENT」または「SMOKING GUN」-拳銃を撃った直後には銃口から煙が出ていることから、決め手となる疑わしい証拠のたとえーと呼ばれる)は内部資料であった。実際、社内資料が訴訟に重大な影響を及ぼすことはよく指摘される。特に、親子会社間のやり取り、たとえば、親会社の法務部から、弁護士の秘匿特権がかからない形で、また、せっかく秘匿特権をかけたとしても、「共通の法的利益があること」を明示せずに秘匿特権が放棄されてしまう形で、子会社のマネジメントへの注意等を行うことは、時として不利益な事実の自白として不利な証拠となる可能性があり注意を要する。
*FORD PINT事件、GM MALIBU事件(いずれもPLの個別訴訟事例)
FORD社の小型車である「PINT」は、ガソリンタンクの位置が後部の床下にあり、追突によって衝撃を受けやすいという設計上の問題があった。実際に、追突された車が炎上し、運転手が死亡し、同乗していた少年が大やけどを負うという悲惨な事故が発生した。原告はディスカバリーを通じて、設計欠陥は事故以前に認識されていたことを発見し、さらに解雇された元副社長の証言で「市場リコール対策を行う費用は今後発生し得る事故による想定賠償金の額を超えるので行わない」という対策の費用対効果の経済計算をしていた社内文書が暴露された。その結果、陪審は人命を軽視した会社の姿勢に対して、通常賠償280万ドルに対して懲罰賠償額としては1億2,500万ドルの賠償支払いを評決した(1978年)。
GMのシボレーMALIBU事件においては技術者が作成した同様の価値分析書類や数多くの証言の結果、懲罰賠償を含む約6,000億円の賠償支払いの評決がなされた(1999年)。
(参考4)社内文書に関する教育とその是非
米国訴訟への対策として、一般に社内文書の作成については以下のような社内教育を行うべきであるといわれている。
・あらゆる社内書類は、秘匿特権等の保護があるものを除き、秘密指定の有無を問わず、すべてディスカバリーで開示されるので、そのことを前提に作成する。
・「読後破棄」という書類は、必ず開示されるきわめて有害な書類であり、作成してはならない。
・「PRIVILEGED & CONFIDENTIAL,ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE,WORK PRODUCT」という表示は、所定の要件を充たす限りにおいて、誤った開示を防止し、また誤った開示をした場合に放棄とみなされることを回避するための日常的な措置として有益である。一方、所定の要件を満たさないものに表示することはかえって有害であり、むやみに表示してはならない。
・書類作成に当たっては、常に事実に即しており、冷静かつ合理的な内容であるべき。根拠のない推測、意見や批判、感情的な表現を含む書類は作ってはいけない。
・特に誤解を生じやすい用語として、粗悪品、欠陥、危険、問題、良い・悪い、失敗、法律違反・・等の用語を用いることには注意する。この点、不利益な事実を認める「自白」とみなされてしまうと、伝聞法則の例外として陪審に証拠として示されてしまうことを肝に銘じるべきである。「仕様に一致しない・仕様を超える/超えない」「案件・関心事」「設計想定と一致しない」「調査が必要」等、客観的な表現を使うよう心掛ける。但し、客観的な表現であっても、「基準に達していない」というような「評価」とみなされる表現は、やはり不利益な事実を認める「自白」となりうるので、注意を要する。そのような評価をすべきコミュニケーションを行なう場合には、可能な限り、秘匿特権を活用することを考えるべきであろう。
・訴訟になればすべての書類が開示されることを常に念頭に置いて、HOT DOCUMENTになる可能性のある書類を作成するときは、表現だけでなく、そもそも作成すべきかどうかから考え、法務部門や外部弁護士と相談する。
・社内の書類保存年限にしたがい、保存年限どおりに保存し、廃棄する。
- しかしながら、上記は、単に訴訟対策として書類の作成等のテクニックを教育したり、隠蔽体質の風土を助長したりするものであってはならない。より重要なことは、このような書類を作成すべき事態を避けるために、問題の発生が想定されるときは、迅速にエスカレーションがなされ、十分な解決がなされる仕組みと文化を醸成することである。弁護士・依頼者間秘匿特権は、「事実」を隠せるものではなく、あくまでも「事実」についての「評価」をする場合に、不用意に不利益な自白とみなされたり、(将来の)相手方に不利な形で濫用されないための道具であり、隠蔽の道具ではないことを肝に銘じる必要がある。
ⅱ)訴訟アラーム時点(訴訟だけでなく、紛争解決条項等により調停や仲裁を行う可能性が高まる時点)
・早期アラームシステムを整備する。訴訟は理由なく始まらない。原因となるべき事項をできるだけ早く把握し、秘密情報の保護・秘匿特権等による保護の仕組みを考慮しながら、末端の情報の関係スタフ、法務部門、マネジメントへのエスカレーション手続を定め、可能な限り訴訟前に解決するか、調停の利用等も有効な選択肢となる場合がある。早期にこれらの手続きに必要な情報が共有される体制を整備する。
特に消費者製品では、製造、出荷、販売、サービスの各段階で、消費者クレームに発展させないような、または、できるだけ迅速に丁寧に解決して、訴訟の契機になるような消費者の不満をためないような仕組みづくりが最も重要である。そのためには、サービス担当者に適切な解決権限を与え迅速な解決に努めるとともに、異常値を可能な限り早く把握できるデータ管理を行う。特にマーケットでの不良・クレーム情報は社内把握だけでなく、WEB等の外部サーチを常時行うことにより、兆候を早くつかみエスカレーション手続につなげ、解決を早く行う。
・弁護士選任、訴訟移行体制整備
・LITIGATION HOLD、秘匿特権等による保護の確実な実施
ⅲ)訴訟提起以後
・できるだけ早い事案把握、ディスカバリー計画準備、訴訟、和解戦略策定等
・訴訟戦略として原告に対して、原告の適格性、主張事実自体の存在に関するディスカバリー(代表原告・被害の特定、対象物の検証要求など)、クラス認定要件に関するディスカバリーおよび請求権(本案)に関するディスカバリーの実施(後述)
・訴訟提起後も、裁判所のアレンジによるものだけでなく、アドホック調停等和解戦略等も重要。特にディスカバリーや証言録取で得られた情報や心証をもとに、和解の戦略を練る。
⑶ 弁護士との秘匿特権(ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE)、WORK PRODUCT特権および情報保護命令(PROTECTIVE ORDER)の概要とその正しい活用について
ディスカバリーに対抗して開示義務を負うことなく、その情報を保護する方法としては、秘匿特権、WORK PRODUCT特権、情報保護命令等の制度があるが、その要件は厳しく、表面的に形式を整えるだけ(たとえば、要件を満たさないにもかかわらず、「PRIVILEGED & CONFIDENTIAL」表示をむやみに使用したり、真に必要な範囲を超えて社内外に配布したりする)の場合には、かえって不利な情報をわざわざ作成して開示させられる結果になりかねない。したがって、このような保護を受ける書類等の作成に当たっては法務部門が関与し、早期に外部の弁護士に法的アドバイスを求めたり、その指示に従った形にしたりする等、必要な要件を満たすべきことを関係者に徹底する必要がある。
➀ 依頼人と弁護士との間の秘匿特権の意義、要件、関連する問題
依頼人と弁護士との間の秘匿特権とは、依頼人が自らの法的な利益の保護のために法的アドバイスを求めるに当たり、弁護士との秘密で自由なコミュニケーションを保障して、開示を拒絶できるという依頼人の権利であり、この権利の保護は、米国においては民事訴訟や仲裁だけでなく、刑事手続、行政調査、差押え・押収の対象からも除外され、開示しなくてよいという強力なものである。
上記のような要請から必要な要件として以下の要件を満たすことが必要である。
ⅰ)「依頼人と秘匿特権の対象となる者との間で」
実務的によく問題になる例は下記のとおりである。
・米国弁護士資格だけでなく他の資格者の取り扱いはどうか
たとえば、日本の弁護士資格は原則、米国弁護士資格と同様に扱われるが、非資格者の法務部員は弁護士の指示に基づきそのコントロールの下に行った相談・調査内容を除き、原則として弁護士との法的コミュニケーションと同様の保護は受けない可能性がある。日本の弁理士資格を持った者に関しては、判例は分かれており、ケースバイケースであり、また規範的な部分だけでなく、認定された具体的な事実状況によっても異なる。
・社内弁護士は社外弁護士と同等に扱われるか
米国では、社内弁護士の場合は、原則、当該企業のビジネス上のコミュニケーションであるという推定が事実上働き、それを覆して「法的アドバイス」であるという事実上の疎明責任が開示者側にあるので、社外弁護士よりも秘匿特権が認められるハードルは高いと考えるべきである。
欧州では雇用関係にある社内弁護士は弁護士会に入会できず、また、秘匿特権の対象ともならない。欧州管轄の社外弁護士によるアドバイスや指示に基づかないコミュニケーションは、原則秘匿特権の対象とならない点が要注意である。日本または米国においては、社内弁護士は原則として法律問題だけでなくビジネス上のアドバイスも行っているとの推定が働くので、名実ともに法的なアドバイスであることを明示するか、早期の外部弁護士の関与が重要である。訴訟の対象となるべき重要な問題に関する秘匿特権の保護のためには、社外弁護士への依頼を介する形式をとるほうが確実である。
ⅱ)「秘密になされた(秘密として維持される)コミュニケーション=通信であって」
・弁護士との相談内容を形式的にも実質的にも秘密に保持し、社内でもその情報を知る必要がある者(need to know)を限定し、その他の者に不必要に配布回覧してはならない。
・ディスカバリー(証言録取)の際に、相手方や第三者に、弁護士と相談した内容を開示すると、権利の放棄とみなされ、保護を受けられなくなる。そのため、証言録取の場合には、「弁護士と相談したか」「その内容は」という質問はOBJECTIONの対象となるので、勝手に答えないで、弁護士の指示に従)。特に、いわゆる関連会社や親子会社間のコミュニケーションであっても、法人格が違う以上、原則として秘匿特権のアンブレラがかからず、せっかくの法的アドバイスであっても、秘匿特権が放棄されてしまう可能性がある点に注意する必要がある。これを防ぐには、COMMON LEGAL INTETEST = つまり共通の「法的」利益がある(ビジネス的には共通の利益であると言えても、法的にはそうでない、という場合もありうる)と言う点を明示し、その実を伴わせることが有益である。
・M&AにおけるDUE DILIGENCE手続等をはじめとする取引の相手方との交渉の中で、紛争等の内容についての弁護士の意見書をはじめとする法的なアドバイスや関連するコミュニケーションを開示してしまうと秘匿特権を放棄したこととされる可能性があるので、その必要性、重要性等を慎重に検討すべき。
ⅲ)「法的なアドバイスを求めるものであること」
弁護士との法的アドバイスを求める内容でなければならず、単に事実を伝えるもの、ビジネス上のアドバイスを求めるものとみられると、秘匿特権の保護は受けられない。この要件は、秘匿特権がかかるかかからないか、のメルクマールとして最も重いものであり、実際のディスカバリーを巡る攻防の中では、鍵となるべき要件である。
・(事実の伝達)
例えば、品質データや顛末・事故記録、社内報告書を弁護士が関与せずに作成してこれを基に法的なアドバイスを求める場合、法的アドバイス部分は秘匿特権が及ぶが、既に存在するデータや事実については保護が及ばず開示に応じなければならない。
一方、問題の発生を認識した当初から法的問題の発生がありうるので、外部の弁護士にアドバイスを求め、弁護士から資料収集、事実調査、検討の指示を受けて行い、弁護士がその情報を不可分のものとして意見書・報告書等としてまとめる場合には、一体として保護を受ける可能性が高まるといわれている。また、このような弁護士の明確な指示に基づき、他の弁護士、社内弁護士、法務部門、その他の関係部門のコントロールの下に守秘義務を負って調査活動を行う場合には、指示をした弁護士に報告するために作成した報告書も秘匿特権の保護が及ぶという主張が可能なので、このような指示や体制を明確にしながら調査を行うことで秘匿特権を活用すべきである。
LITIGATION HOLD義務が発生した場合に、弁護士が関与せず、法務部や関係部門が調査をしてまとめ、事後的に弁護士が関与しても、上記のとおり事実調査や報告内容については秘匿特権の保護が与えられない可能性があり、その結果、わざわざ問題を収集整理して新たに文書を作成することは、不利な状況を自ら作り出して開示させられることになりかねず、このような拙速な行動は厳に避けるべきである。(但し、例えば、ニューヨーク州等では、いわゆるAnticipation Litigationの法理によって、開示の例外となりうる場合があり、また、事後的な外部弁護士の関与であっても、その弁護士への報告という形で、それまでの訴訟・仲裁対策のコミュニケーションをまとめておくと、「これらは外部弁護士に法的なアドバイスを求めるために、その準備として社内で行なったものであり、秘匿特権の対象になるはずである」という議論も、100パーセント確実ではないが、有益な場合もあり、そのような行動をとってしまった場合には直ちに弁護士と相談すべきである。)
・(法的アドバイスではなくビジネス上のアドバイスとして見られる場合)
社内弁護士が各部門の問い合わせに答えたり、アドバイスを行う際、純粋な法的なアドバイスを超えて、ビジネス上のアドバイスを含めて行うことは、事業内容や実務を理解している社内弁護士の役割として求められることも多いと思われ、社内弁護士の利点であると思われる。しかし、米国訴訟や仲裁におけるDISCOVERY対策の観点からは、社内弁護士がビジネスに関するアドバイスを法的なアドバイスに合わせて行っている場合には、法的なアドバイスを超えたものとして秘匿特権の対象とならないケースがありうる。
法的アドバイスとビジネス上のアドバイスを区分することは困難な場合もあり、社内弁護士の在り方としては、訴訟になる可能性のある事案では、純粋な法的なアドバイスは形式・内容とも法的相談を求められた結果であることが証明できるよう、「提示された事実関係の真偽は確認できていないが、これを前提にする限り法的アドバイスとして・・」という形式にして事実関係に踏み込まず、また、ビジネス上のアドバイスではないことを明示した報告書等を作成するか、初めから事実調査を含めて外部弁護士の指示に従い報告書を作成することを検討すべきであろう。
② 秘匿特権のディスカバリーにおける取り扱いと留意点
ⅰ)PRIVILEGED & CONFIDENTIALという表示を書類等につけて秘匿特権を主張できるようにすることはよく行われるが、このような表示は真に秘匿特権の保護を受けるべきものに限り、書類等のタイトルまたは欄外に目立つ形で表示する。また、表示した書類等の配布範囲にも留意する。
ⅱ)ディスカバリー手続においては、タイトル、PRIVILEGE表示の有無、作成日時、作成者、作成目的を明示して、秘匿特権がある書類等のリスト(PRIVILEGE LOGと呼ばれる)を作成して、相手方に提示しなければならず、要求があれば作成の経緯・事情について説明する必要があるので、特に注意する。また、これらの作業をしておくことによって、万一誤って開示してしまった場合にも、その撤回を正当に行い、秘匿特権の保護を維持できる可能性も高まるので、有益である。
③ WORK PRODUCT制度による保護
WORK PRODUCTとは、訴訟の提起が予期できるときに、弁護士のため、または弁護士による調査、意見・アドバイス、訴訟準備等の目的のために作成される書類等は、弁護士の活動を保護するために、ディスカバリーの対象とならないという制度である。
弁護士に関する秘匿特権のうちの一つの形態であるが、ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGEと異なる点は、ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGEは弁護士とのコミュニケーションを保護するための依頼人の権利であり、要件として、弁護士との法的アドバイスに関するコミュニケーションである必要があるものの、その保護は非常に強力である。これに対して、WORK PRODUCTは、「訴訟提起を予期できる場合(in anticipation of a litigation)」という限定条件の下ながら、弁護士のためにその指示を受けて会社関係者、外部関係者が作成する資料等もこの法理の保護を受ける等、保護範囲が広い一方、訴訟において他の証明手段がない場合には裁判所の命令により開示させられる可能性があるという意味で保護の限界があるといわれる。
「訴訟の提起を予期できる」という時点は、LITIGATION HOLDの義務が発生する時点との関係上、この法理による保護を主張する書類を作成した以上、その時点からLITIGATION HOLD義務が発生するという逆の議論があり得るので、必ず弁護士が関与して、書類の作成については万全を期すとともに、あわせてATTORNEY-CLIENT PRIVILEGEの保護を受けるとともに、LITIGATION HOLDの義務を開始するよう、弁護士の指示を受けることが重要である。
④ PROTECTIVE ORDER制度による保護
HOT DOCUMENTSを含めて、ディスカバリーにより開示される情報に企業秘密やプライバシー情報等が含まれている場合には、その部分を特定して裁判所に対して秘密保護の申し立てを行うことができる。裁判所がPROTECTIVE ORDERを認める場合、関係部分を黒塗り(マスキング)したり、相手方の弁護士だけが見ることができる措置(LAWYER’S EYES ONLY)、裁判所だけが見ることができる措置(IN CAMERA)等、企業秘密等が流出しないような保護を受けることができる。
(参考5)弁護士の関与による秘匿特権の保護と国際調査、わが国制度との比較
秘匿特権の保護は、弁護士の立会権とともに、公権力に対して対抗するための公益的役割を負う弁護士制度の歴史的背景と深くかかわっており、英米法系の国では民事訴訟だけでなく、独禁法違反・贈収賄等の刑事・行政調査や第三者委員会調査における個人保護等においても、その保護は確立している。したがって、上記の留意点は欧米当局による司法・行政調査にあたってもほぼ同様に考慮すべきである。これに対して、わが国では、刑事手続においてそもそも弁護士立会権を認めず、弁護士の義務として依頼者の秘密自体の保持義務・特権はあるが十分ではなく、特に秘匿特権等はまったく認められていない。したがって、独禁法違反等の案件でわが国での立入検査や供述内容として、弁護士が関与して作成した書類等もわが国の当局は開示させたいとの思惑もあり、近時も検察当局による捜査において、対象企業から、社内弁護士が関与して作成されたと思われる書類だけでなく、そのパソコンも含めて押収したという報道がされているところである[1]。[1] リニア中央新幹線をめぐる入札談合事件捜査に関する日本経済新聞2018年2月2日記事参照
いったん任意に開示されてしまうと秘匿特権を失い、国際協力により他の規制当局に開示される可能性も否定はできない。したがって、開示の要求に対しては弁護士の立会や関与を求めたり、仮に開示したりする場合にも、他のディスカバリーのある管轄における訴訟や仲裁等において、本来保護されるべき秘匿特権を放棄するものではない、等の留保を明記する等(これでも確実に保護されるものではないが、少なくとも、留保を付けない場合より、保護される可能性や交渉の余地を残すことになる)、特に注意する必要がある。グローバルに規制や調査等のハーモナイゼーションが進んでいる中で、わが国においては秘匿特権等の保護が認められていないことは、調査におけるデュープロセスの保護や調査に対する武器平等性を欠いている点で先進国の法制としては極めて異例であり、わが国の制度に関する立法的な課題として長年議論がなされている。
5.クラスアクションの防御戦略
クラスアクションが提起された場合、後述する和解を検討する場合を含め、以下のような段階を踏んで、経験ある弁護士・ディスカバリーベンダーの意見を求め、防御戦略を検討することが必要である。
⑴ 訴訟提起前(訴訟が予期できる時点)
➀ クラスアクションの戦略に詳しい経験豊富な弁護士をできるだけ早く選任する。
訴訟が予期できるときからLITIGATION HOLDの義務があり、訴訟戦略をできるだけ早期に立てるためには、問題が起きてからではなく、普段からいくつかの経験ある弁護士事務所を候補として用意し、緊急時にはその中から最適な事務所を選ぶことが必要である。候補となる事務所は業種・業態によるが、大事務所だけでなく、一定の専門分野のクラスアクションに極めて強いといわれる専門事務所(ブティック型の事務所と呼ばれる)を含めて、米国子会社の社内弁護士のネットワークや経験のある日本の法律事務所から、候補先の推薦を受けたり、クロスボーダー案件への経験と対応力があるグローバルファームに相談したりすることが望ましい。
訴訟等の紛争が予期されるか、実際に訴訟等が提起された場合には、複数の候補法律事務所に対して、事案の概要、訴訟の相手方弁護士名、訴訟提起地を示したうえで、RFP(REQUEST FOR PROPOSAL)として、訴訟等の戦略の概要、見通し、相手方弁護士・訴訟地等の特徴、訴訟等の背景となる専門的技術的問題への精通度、日本企業への理解・経験の有無、担当弁護士およびディスカバリーベンダーの体制、スタフィング、各スタフの専門性の有無およびコスト予想(Fee Construction)等を1週間程度で提出させ、最終決定に当たっては関係の弁護士等の立会いの下、プレゼンテーションを行ってもらい、追加インタビューを行い、対象ビジネスや技術への理解度、専門性、信頼性、コミュニケーション力、コスト管理力を比較し、確認してから決定することが望ましい(この手続はBEAUTY CONTESTと呼ばれる)。
② LITIGATION HOLDを開始するとともに、秘匿特権・WORK PRODUCTを活用しながら、HOT DOCUMENTの有無、社内のKEY CUSTODIAN、証人となるべき関係者の有無、さまざまなデータ等の関係情報の迅速な収集を通じて、事案の強み弱みをできるだけ早く把握することが、最も重要である。そのことにより、訴訟等の基本戦略、タイミングを含めた和解の検討、コスト管理、ディスカバリー計画他スケジュール管理、裁判所への対応計画を立てることが可能になり、訴訟等への効率的で有効な対策を立てることができる。
③ ディスカバリーのコストの低減も一緒に検討し、経験あるディスカバリーベンダーも早期に選任して、ディスカバリーの範囲、方法、負担をできるだけ早く検討する。
⑵ 訴状送達・訴答段階
訴訟の冒頭手続での防御としては、送達手続、管轄を理由とする却下、移送、統合を検討する。
➀送達手続
訴訟としての効力発生のためには、基本的に被告に訴状が適式に送達されることが必要である。まず、米国から日本の会社・事務所等への直接送達に関しては、これを認めず、ハーグ条約に則った外交ルートによる正式送達を求める(日本の裁判所を経由して、翻訳とともに送達される)ことを検討すべきであろう。ケースによるが、州によっては直接送達を有効とする考え方がある。さらに、外交ルートによる正式再送達を求めた場合、数か月かかることが通例であるとしてもいずれ送達されるのだから手続で争うべきでないという考え方がありうるが、十分な準備時間をとれるメリットもあり、弁護士と相談すべきであろう。
なお、特にカリフォルニア州においては、米国子会社は本社の「総務部長」に該当し、ハーグ条約によらない米国子会社への直接送達でも正式な送達としての効力を認めたケースがある。そのために、米国子会社では、日本の親会社への送達がなされてもこれを受け取らない等の方法も検討しておくべきであろう。
②管轄の争い
管轄の議論として、事物管轄、人的管轄等、複雑な議論があるが、ここでは一般論は省略し、特にクラスアクションの管轄をめぐる争いで問題とされる、連邦管轄権の及ぶ場合について、「完全な州籍相違」の場合に加えて、CAFA(Class Action Fairness Act:クラスアクション公正法)による追加管轄の拡大がなされているので、これらの連邦管轄に関する考え方について解説する。
まず、一般に連邦が管轄を有する場合として、「完全な州籍相違」の場合は、原告の州籍と被告全員の州籍が異なっており、かつ、原則としてクラスの各メンバーの訴額が75,000ドルを超えていることが必要である。しかし、CAFAでは、管轄要件を緩和し、クラスの構成員が100人以上で、原告のいずれか一人と被告のいずれか一人(米国外を含む)の州籍が異なり、かつ、紛争総額合計が500万ドルを超えていれば連邦管轄が認められるとしている。外国企業を被告とするクラスアクションは訴額がかなり小さい場合を除き、特定州で提起されたクラスアクションを連邦の管轄に移送することで、州裁判所に比べ、比較的安定しているといわれる連邦裁判所による審理を求めることができる。
(参考6)Tort Reform運動とClass actionの適正化
(参考7)“MAGIC JURISDICTION“の実態
“What I call the ”magic jurisdiction”[is] where the judiciary is elected with the verdict Money.The trial lawyers have established relationships with judges that are elected ;they are State Court Judges; They are populists;….it’s a political force in their jurisdiction, and it’s almost impossible to get a fair trial if you’re a defendant in some of these places..”(Richard Scruggs)
③訴訟地の争い、却下、移送
米国では、管轄が生じるいくつかの裁判所のうち、当事者にとって正義を実現でき、公平で便利な裁判所を決定する基準としてよく争われるものとして、人的管轄権、裁判地(VENUE)の考え方、Forum ShoppingとForum Non Conveniens 抗弁、裁判地選択条項と、これらによる移送、却下がある。訴訟の冒頭の管轄の争いによって紛争を終わらせることができるかどうかについては、米国弁護士のアドバイスを受けるべきである。
④仲裁条項による強制仲裁の申し立て(連邦最高裁判決)
有効と判断されるために一定の要件を満たす必要があるが、あらかじめクラスアクション・陪審審理、クラス仲裁を排除(CLASS ACTION WAIVER)し、個別仲裁に付す仲裁合意条項があれば、個別仲裁強制の申し立てを行うことができる。2011年には、連邦最高裁において、連邦仲裁法が州法の規定に優先するという連邦法優越理論(FEDERAL PREEMPTION)に基づき、このような仲裁合意条項が州法上無効であるとして提起されたクラスアクションを、連邦仲裁法の目的を損なうものであるという理由で却下するという判断がなされた(参考8)。
クラスアクションではなく個別仲裁に付されることで、多数消費者との紛争は個々の消費者との個別紛争になり、専門家である仲裁人が手続を進め判断するため(原則として仲裁判断は最終で上訴手続はない)、陪審審理手続はなく、集団性を立証するための広範なディスカバリ―や様々な巨額の手続費用はかからず、何よりもクラスアクションにより巨額の弁護士費用を狙う原告弁護士は、個別案件については興味がないため、クラスアクションにつきものの集団を背景とした原告弁護士の圧力はないといわれる。事業者にとっては、消費者側の手続費用を負担したとしても、大きなメリットがあるといわれ、消費者契約や労働契約にはこのような仲裁条項が合意される例が一般化したといわれている。
(参考8)AT&T MOBILITY LLC v.CONCEPCION連邦最高裁判決とその限界
強制仲裁条項の有効性を初めて認めた連邦最高裁判決(AT&T MOBILITY LLC v.CONCEPCION)の要旨は以下のとおりである。
AT&Tが携帯電話の販売において、Free Phoneと広告宣伝しながら実際には30ドル程度の消費税がかかることを表示しないで販売したことは消費者詐欺等にあたり違法であるとして、原告はクラスアクションを提起した。被告のATTは、各消費者と締結したサービス契約に、すべての紛争はクラスアクション、クラスとしての集団仲裁によらず、個別の仲裁により解決されるという趣旨の強制仲裁条項があることから、クラスアクションによるべきではないとして却下を求めた。これに対してカリフォルニアの連邦地方裁判所、連邦控訴審裁判所は、このような仲裁条項は消費者の権利を制限するものでカリフォルニア州法に基づき「非良心的である(UNCONCIONABLE)」との理由で無効としたので、事件は連邦最高裁に上告された。連邦最高裁は、連邦法の州法への優越法理(FEDERAL PREEMPTION)により、州法は、たとえ消費者保護という別の政策目的を実現するためのものであっても、連邦仲裁法の目的(簡易迅速な手続きで紛争を解決するための仲裁合意の執行確保)と矛盾する手続きを強制することはできず、連邦仲裁法に基づいて個別強制仲裁合意の効力が認められるべきであるとして、クラスアクションを却下した。
この判決以降も強制仲裁条項の有効性は何度も争われたが、以下のような要件(CONSUMER-FRIENDLY CLAUSEといわれる)を満たしている場合には有効性が認められる場合が多く、米国においてはクラスアクションの回避のために、消費者契約や労働契約等にこのような強制個別仲裁条項を入れることが一般化しているといわれている。
・理由のない申立てを除き、仲裁費用を被告企業が負う。
・仲裁は原告の住所地で行う。
・仲裁人選任前に被告企業が提示した和解額よりも仲裁の結果示された賠償金額のほうが高くなった場合、被告企業は一定額(AT&T事件の場合は7,500ドルおよび弁護士費用の倍額を支払う)。
・消費者は自由にオプトアウトできる。
しかし、消費者金融や労働者保護の分野で法規制としてこのような強制仲裁条項を無効とする動きがあり、注意を要する。また、クラスアクションだけでなくクラス仲裁を含めて放棄する条項の有効性については、仲裁条項にその旨を明確に記載しなければ認められないとする裁判例もあり、強制仲裁条項を設定する場合には、その条項の具体的な内容について専門家と相談すべきであろう。
(なお、わが国においては、仲裁法附則3条2項で消費者と事業者間の仲裁契約について、消費者は原則としていつでも解除できるとの消費者保護規制があり、また、同附則4条で将来の個別労働関係紛争についての仲裁合意は無効とされており、米国とは明らかに取り扱いが異なることに注意すべきである。)
(参考9)不特定多数の消費者とどのようにしたら契約関係(PRIVITY)を成立させうるか?
強制仲裁条項が有効だとしても、不特定多数の消費者との間でどのように仲裁契約を成立させることができるかという点でも争いがある。サービス契約の場合、製品に契約書を同梱して返送を依頼してもほとんど返送されないことから、梱包の表面に契約書が見える形で添付してシュリンクラップで覆い、梱包を破ったら添付された契約内容で成立するという警告を入れて契約成立とみなすという方法(「シュリンクラップ契約」)の有効性は何度か争われた。しかし、契約意思の確認という意味で有効性が認められないとされる例も多く、その有効性については確定したとはいいがたいといわれる。
一方、ソフトウェア契約のようにWEB上等で「承諾」等のボタンをクリックすることで契約の成立を認めることができるか(「クリックラップ契約」の有効性)については、消費者等の権利や承諾の方法についてわかりやすく明確に示され、消費者が慎重に判断したといえるような場合には原則として有効とされるが、なお有効性を争われる例があるので、このような仕組みを設計する場合は専門家に意見を求める等、注意すべきであろう。
⑤ 統合等
大規模な事故、広汎な製品事故、独禁法違反等、共通する原因に基づいて複数の州でクラスアクションが提起された場合には、MDL(広域係属訴訟:MULTI DITRICT LITIGATION)として、連邦裁判所の熟達した裁判官によるパネルが組成され、その管理のもとにおかれる裁判所に各訴訟を移送し、統合することが可能となる。MDL制度においては複数のクラスアクションでの陪審手続前のさまざまな手続、特にディスカバリーの重複が避けられるとともに、複数の裁判所での判断の不一致を避けられるメリットがある。また、原告側(被告側)の弁護士も多数に上ることから、リードカウンセル(裁判所に対応する代表弁護士で、連絡調整役となる)が定められ、できるだけ効率よく手続を進める工夫がなされる。
⑶ 訴答・ディスカバリー段階
➀訴答とMOTION
訴答とは、訴状で特定された事実上、法律上の主張に対して、認否や積極的な主張、反論等を行うものである。米国では被告側の反論は訴答段階で主張しなければその後の手続では反論を追加することが制限される場合があるので、認否にとどまらず、積極的な反論や想定されるあらゆる主張をしておく必要がある。
訴答の前に、よくなされる被告の防御のための手続的な申し立てとしては、訴訟の理由となっている請求の内容が明らかでないので明確化させ(MOTION TO CLARIFY)、いくつかの訴因のうち関係のないもの、理由のないもの等を訴状等から落とさせる(MOTION TO STRIKE)ことにより争点を減らし、場合によっては訴訟全体の却下を求める(MOTION TO DISMISS)等の申し立てがなされることが一般的である。
この却下申し立ての理由としては、送達手続違反、管轄違い、FORUM NON CONVENIENS、訴状の不備等の手続的なものと、より実体面に近い主張として、MOTION FOR FAILURE TO STATE CLAIM(DEMURRERと呼ばれる州もある)が多用される。仮にすべての訴状の記述が真実だとしても原告の請求を理由づけるに足りないような場合(たとえば、一見して請求に理由がないか、主張を裏付ける事実の指摘がなされておらず、「確からしさ」に欠けているような場合。また、請求の要件のうち、例えば違法な行為の態様は記載されているがどのような損害を被ったかが記載されていない等、請求に必要な要件が欠けている、時効にかかっていること等も理由となる)がこれに当たる。但し、裁判所はただちに全面却下することには慎重であり、技術的な面で訴状の記載が不十分であると判断すれば訴状の補正追加を求めるので、却下がされる場合は限られるが、それでもこのような申し立てによって争点を絞り、明確化させ、準備の時間をとれるというメリットがあるので、弁護士と相談すべきであろう。
② 原告側への積極的なディスカバリーによるFRIVOLOUS訴訟の印象付け・抗弁
クラスアクションは往々にして原告弁護士が主導して、具体的な問題や被害が共通していないにもかかわらず、訴訟さえ起こせば和解で相当の弁護士費用が稼げるとの皮算用の下で、時として根拠がない(FRIVOLOUS)訴訟が提起されるという濫用が指摘されてきた。事例によっては、代表原告には全く具体的な被害がなく、訴訟自体を全く理解していないにもかかわらず、インセンティブをもらえるという原告弁護士の甘言にのせられ、代表原告に祭り上げられていような例も実際に指摘された。
ディスカバリーは一般に原告から被告に対してきわめてアグレッシブになされる一方、被告から原告に対するディスカバリーはあまりなされない傾向にあるが、このようなFRIVOLOUSな訴訟である可能性が高い場合には、積極的に被害内容を特定させ、対象の製品等のINSPECTION(検証要求)や原告自身の経験について証言録取を求めることが有効な場合がある。最終的に却下されないまでも請求内容が弱いことが露呈し、有利な和解に至るケースもあるので、初期の防御戦術として検討すべきであろう。
(参考10)原告に対するディスカバリー、デポジションの実例
製品の不具合を理由とするクラスアクションで、代表原告から購入の記録を求め、不具合の状況を原告に対する証言録取で確認したところ、「購入していないし、不具合についても聞いたことがない」「原告弁護士とは初めて会った」「頼まれてきただけ」等と、訴訟そのものを原告弁護士がフレームアップしたに過ぎないことが判明したケースがあり、ただちに却下され、裁判所は制裁として被告の関連費用の賠償を原告弁護士に命じたケースが実際にある。
(但し、事前に調査して確実に根拠がないとの心証がある場合に限って行うべきであり、逆の事実が判明すると裁判所に原告主張の正しさを強く印象付け逆効果になる)。
(参考11)クラスアクションにおける原告弁護士の立場と思惑
クラスアクションは、訴訟提起時にはクラスアクションとして必要な要件を備えているかどうかは審査されず(むしろ訴状の内容は一応真実であると仮定される)、しかも、わが国の消費者裁判手続特例法と異なり、原告となれる者を特定団体に限るといった制限はないので、誰でも(一人でも)、同様な被害を被った多数の被害者を代表して、巨大な訴訟を提起することも可能である(大規模事故、PL、差別問題、証券詐欺、消費者詐欺等では、その対象者は100万人レベルということもある)。その結果、クラス全体としてみれば、一人の被害は小さくともその経済的な価値総額は巨額に上る可能性がある。原告弁護士はこのような経済価値総額に関する巨額な弁護士費用を求めて、たとえば次のような行動をとっているといわれる。
・WEB等で常にクラスアクションの対象となる被害者を募集して、一定数集まると、事案を調査し、原告の主張が通りやすく有利な裁判地・裁判所に提起するために、最も都合の良い代表原告を探し出して選ぶ。その際、いわゆる完全成功報酬制度(着手金は事実上取らないで、勝訴または和解で得た経済利益の最大1/3程度の成功報酬を手に入れる)により、原告の負担なく訴訟の提起を行うことができ、さらに勝訴または和解に至る場合、代表原告には数千ドルから数万ドル程度のインセンティブ支払いが認められるので、代表原告は本来の代表原告の適格性がないにもかかわらず、原告弁護士からの依頼に応じているケースもある。過去には有名な原告弁護士事務所が特定の原告にキックバックをわたして継続的に代表原告として利用していたため、刑事告発されたケースすらある(MILBERG WEISS事件等)
・しかし、原告弁護士にもリスクがつきまとう。訴訟提起、ディスカバリーに係る巨額の費用負担をかけていながら敗訴すると、成功報酬は払われず、すべて自らの負担になりかねない。クラスアクションは、原告弁護士にとっては、いわばハイリスク・ハイリターンのギャンブル的要素の強い投資であるといわれることすらある。したがって、原告弁護士にも、本当はコストをかけず、相当額で早く和解したいとする強い動機があり、その極端な例として、根拠は薄いにもかかわらず被告を恐喝的に追い込んで和解を成立させたり(BLACKMAIL SETTLEMENT)、被告と通謀して弁護士費用を確保できればクラスの利益を犠牲にして不利な和解をする(SWEETHEART SETTLEMENT)等、濫用の要因になるといわれている(後述、和解戦略参照)。
③ クラス認定と本案に係るディスカバリーの二分化(BIFURCATION)と訴訟戦略
ディスカバリー、特に書類やデータ等、最も大量に提出されるものについては、訴訟の段階に合わせて、以下のような戦略的考慮がなされる場合が多い。
被告からのイニシャル・ディスカバリーの後、ディスカバリースケジュールとして、事案に合わせた書類・情報の範囲、関係者の範囲、提出の形式、ソートを行う用語の選択、翻訳の有無、分割スケジュール(いわゆるROLLING ベースでの提出の可否)等が協議されるが、原告弁護士は広汎で一方的な要求を行い、被告を困惑させたり、無駄な費用をかけさせたりして、有利な和解に持ち込もうと迫ってくることもある。
これに対して、初期のディスカバリーでは、後述するクラス認定に必要な範囲に限定した証拠等と、原告の主張に基づく実体的な証拠(本案)等を分け、被告側の負担やコストの無駄を省くため、クラス認定に必要な範囲に限りディスカバリーの範囲を制限する申し立てを行うことも多い(BIFURCATION:二分化)。また、必要な技術的な情報についてはPROTECTIVE ORDERを求めることで、原告の広汎かつ一方的な請求を制限できる。
さらに、あまりに広汎で、負担が大きすぎる、収集困難な(UNDULY BURDEN、INACCESSIBLE)ディスカバリーについては、事案との関連性(RELEVANCE)の明確化を求めたり、ディスカバリーコストの負担を相手方に求めるMOTION(MOTION FOR SHIFTING THE BURDEN OF DISCOVERY)を提出したりすることが有効な場合がある。
このような努力を積み重ねることは、手続全体に対するコントロールを維持し、さらに証拠が早期に開示されてしまうことによる負担やその後の不利な展開を避ける結果ともなり、訴訟の進行戦略、特に和解のタイミングを計る意味でも重要である。
⑷ サマリージャッジメント(SUMMARY JUDGMENT:略式判決)段階
サマリージャッジメント(略式判決)とは、原告被告の主張が出そろい、その基礎となる重要な事実(証拠)について争いがない場合、その重要な事実に関する争点について、陪審審理に進むまでもなく、裁判所だけで行う判断・手続きをいう。事実の争いがないことを前提に行う判断であるので、サマリージャッジメントを求める申し立て(MOTION FOR SUMMARY JUDGMENT)ができる場合は限られるものの、クラス認定の前に主要争点について略式判決が出されれば、陪審審理を経ずしてクラスアクションを抑制する効果が期待でき、訴訟戦略としては重要である。
(参考12)サマリージャッジメントが認められうる事例
⑸ クラス認定段階
➀クラス認定とはなにか。その意義と訴訟の勝敗
クラスアクションは、被告の行為によって同じ被害を受けている多くの被害者を代表するとして、最低一人の代表原告がいわば勝手に始めることができ、訴状の内容は一応真実であるとして仮定されるが、さまざまな手続やディスカバリーによって、その集団的な請求が本当に、原因、因果関係や損害についてクラスの構成員に共通しており(共通性)、共通している事項が構成員の個別の事情を超えて支配的であり(支配性)、そしてそのような被害者が多数いること(多数性)に加え、代表原告の被害がクラスに共通する典型例で、その原告弁護士を含めてクラスを適切に代表することができるか(典型性、適切代表性)等を認定する手続を経て初めて成立するものである。もし、クラス認定がされた場合には、些細なミスによる被害額が一人当たりは少額でも(たとえば10ドル)、被害者が10万人いればその価値は100万ドル(1億円レベル)の訴訟となるが、もしクラス認定が認められなければ一人の原告のただの10ドルの訴訟となって、原告にとっても原告側弁護士にとっても訴訟は費用だけがかかるまったく意味をなさないものとなる(このような状態を「DEATH KNELL(弔いを告げる鐘)」といい、クラス認定がされなければ、原告は訴訟を取り下げ、訴訟の終了となる)。逆に、クラス認定がされると、その結果(クラスの範囲を定め、共通の原因による共通の被害があるものと認められ、その構成員とされるメンバーにその効力はすべておよぶ)、クラスに対する共通の損害賠償義務を基礎づける共通の原因または被害がある前提でその後の手続は進むため、引き続き本案(実体的な損害、請求内容)についてディスカバリーがなされ、陪審審理において具体的な審理がなされるとしても、事実上、クラス認定を前提に陪審がどのような判断を示すかは予測することができず、被告にとっては巨額敗訴のリスクの可能性は一気に高まる。
したがって、クラス認定は原告にとっても、被告にとっても、勝敗に決定的な影響を与えるものであるので、クラス認定の要件の成立をめぐっては相互に攻撃防御方法を尽くす最大の山場であることが通例である。和解のタイミングとしてもクラス認定の後になれば、いわば負け戦を認めた敗戦処理に近づくため、できるだけ交渉力を残す形で、クラス認定前に行うことが多い。
② クラス認定要件の意義(成立要件、立証責任)、濫用への制限動向
クラスアクションが成立するために必要な要件としては、1.⑵で記載したとおり、共通性、多数性、典型性、代表の適切性、支配性、優越性等があり、これらはすべてクラスの成立要件であるので、代表原告によってすべてについて主張・立証されなければならない。しかし、伝統的な米国裁判制度の当事者主義および裁判所と陪審との役割分担の考え方に加え、裁判所の運用としても、クラスアクションを入り口で門前払いすることには消極的で、従来、成立要件はきわめて緩やかに解釈され、濫用の引き金になってきたといわれてきた。このような批判に対して、2011年以降、連邦最高裁は相次いで、主要な要件について手続要件から実質的に実体要件に変化したのではないかといわれるような厳格化を行い、濫用の制限を行ってきており、その基本的な方向は現在に至るまで変わっていない。したがって、被告側の防御も以下の判例等(参考13から参考18)を参考に、いかに成立要件の立証を阻止するかに重点が置かれている。
(参考13)WALMART事件連邦最高裁判決―「共通性」立証要件の実体化・厳格化
この判決では、(ⅰ)原告が、具体的で中心的な争点が共通であり、現実に存在していること(共通性)について証明責任(証拠の優越基準)を果たしているかどうか判断するためには本案に踏み込むこともやむを得ないと明示したこと、(ⅱ)共通の原因によって、同じ被害を被っていることを示さなければならないことを証明の対象として明示したこと、(ⅲ)これらの結果として、従来クラス認定は手続要件と理解されてきたところが、ある程度の本案の裏付けを伴って、クラスの主張全体が本案に進んでも一貫していることが事実上求められるようになったこと、という点で画期的であり、裁判所が厳しいゲートキーパーの役割を負うことを示したものと評価され、以後のクラスアクションに関する裁判実務に多大な影響を与えている。
(参考14) COMCAST事件連邦最高裁判決―共通争点の支配性要件の厳格化
上記の通り、共通性の要件が強化されたことをベースに、共通争点の支配性(PREDOMINANCE)の要件についても、WALMART判決の趣旨が同様に適用されるとして、この判決により、本案の判断とクラス認定要件である支配性の要件は重複し、また支配性の証明は厳格化されることが明示された。この支配性の要件により、必ずしも請求が一体であるとは言えない多くの金銭請求を糾合する、いわゆるオプトアウト型クラスアクションの場合には、請求根拠が共通するだけでは足りず、連邦規則23条(b)(3)により、クラス構成員に個別に生じる様々な事情の差を超えて共通争点が支配的であること(the questions of law or fact common to class members predominate over any questions affecting only individual members)が必要とされる。この判決は、独禁法違反の事案で、違法行為による損害について、本案である独禁法違反の認定事実に一致した、クラス全体に適用される損害算定方法を示し、その損害算定方法は、個別の事情を超えて共通した一つの算定方法で損害額の立証ができることを証明する責任を負うことを示したため、支配性の要件は格段に厳格化されたといわれている。
これら二つの連邦最高裁判決により、原告は「共通性」としてその点を解決すればすべての問題が解決するという程度の核心の争点に関して、共通の原因によって同じ被害を受けたこと(因果関係を含む)について、本案に踏み込んで厳しい分析(RIGOROUS ANALYSIS)を行うとともに、「支配性」についても、その共通争点が支配的というためには、損害についても、本案の主張と符合する算定方法として共通した一つの計算方法で算出できるということが必要であり、損害に関するそのような厳格な立証責任を代表原告が負うことが明確になったといわれている。
これらのクラスアクションの成立要件に関連した連邦最高裁判決は、結果としてみれば、クラス認定の段階で、共通性、支配性等の要件に関してクラス全体に共通する問題の核心に関する実体に踏み込んで原告に証明責任を負わせるという形で、クラスアクションを適切に規律しようとするものである。
(参考15)独禁法違反事件とクラスアクション
独禁法違反によるクラスアクションでは、司法取引で有罪答弁を行うと、違反行為やその違法性では争えなくなり、そのような企業にとっては因果関係や損害という共通性、支配性、典型性等という要件に関して、代表原告がクラスの共通した損害発生をどこまで証明すべきかについて争い、できるだけ和解によって支払額を軽減することが中心とならざるを得ない。特にカルテルの結果、直接被害を受けた直接購入者とそれ以外の間接購入者では、利害の対立があるため、解決を複雑にし、また、被害者が大手企業の場合、より良い解決を求めてオプトアウトして別訴で争ってくる傾向もあり、これを慫慂するいわゆるオプトアウト・バーと呼ばれる弁護士もいることが指摘されている。
(参考16)典型性、代表の適切性をめぐる防御
例えば、医療用具(インプラント等)によるPL事故については、人によって医療用具の特性に対する適応性や被害の因果関係が異なるので、共通性とともに典型性はないとされる。また、同じ原因物質に汚染されたとしても、症状が出ている人と出ていない人がいる場合には、それぞれのグループの区別を無視してこれらを一つのクラスとしてみると、共通性・支配性・典型性がないだけでなく、将来の被害の発生を巡り、利害対立を生じる可能性があるので、代表原告は代表の適切性に欠けるとされる(このような場合はクラスを分けて代表原告を別にすべき)。
このように、共通性、典型性、適切代表性、支配性はしばしばセットとして主張される最も重要な論点であり、事案を徹底的に分析して、共通性の否定をベースにこれらに該当しない事項、データ等の事実に、専門家証人による理論的な証言を合わせて、クラス認定を阻止することが通例である。
(参考17)優越性、多数性、ACERTAINABILITY、原告適格を巡る議論
優越性とは、他の救済手段よりクラスアクションによる救済が効率的、経済的で優れていることを示すものなので、例えばリコールをしたほうが被害者の直接救済になると考えられる場合には、わざわざ個別の被害を集団的に金銭賠償として認めることには優越性がないとする判例がある。また、米国では、州によって、不法行為の成立要件が異なり、全米を一つのクラスと見ると一つの訴訟として管理することは困難であるので(管理可能性、MANAGEABILITY)、このような場合も優越性がないとされる。また、クラス認定を行う際、クラスの定義として「(ある商品を買った)消費者全員」というような抽象的な特定だけでは足りず、個別の個人(住所氏名)を最終的に特定できなければ、クラス認定後個別通知を行い、オプトアウトや救済申請を受け付けることができないので、少なくとも特定できる見通しがなければ、ACERTAINABILITY(クラス構成員が具体的に特定できる可能性があること)がないとして、却下されたケースもある(但し、客観的に特定可能性があれば、実際に特定できるかどうかは問わないとする判例もあり、判断は分かれている)。
さらに最近の連邦最高裁判例では、いわゆる業法違反は明確にあるが、実際の被害が明確でない場合(たとえば、インターネットによる個人の公開情報収集業者が集めた個人に関する情報が間違っている場合、必要な注意義務を尽くしていないという意味では法令違反になるが、例えば年齢を間違っていた場合、実際の被害が発生したとまでは言えないケースが多い)には、そもそも連邦憲法では、具体的な被害がない場合、連邦裁判所で取り扱うべき紛争性(CASE OR CONTROVERSY)がないために、原告適格(STANDING TO SUE)をそもそも欠いているかどうかの審理を尽くすべきであるという理由(修正憲法3条)で連邦控訴審裁判所に差戻す判決が出されており、大きな話題をよんでいる(SPOKEO事件)。さらに、個人情報の漏洩に関するクラスアクションでは、漏洩がされてしまったことは否定できない事実であるがそれだけで損害とみる考え方、具体的に例えばクレジットカード情報が悪用され実害があるような場合に限るという考え方、あるいは、具体的な損害が必要とまではいわないがその危険性が極めて高いことが必要であるという考え方が、連邦控訴審レベルで対立しており、クラスアクションの要件以前の議論として注目されている。
(参考18)SPOKEO事件連邦最高裁判決―原告適格
米国連邦司法制度を利用しようとする場合の要件としては、米国憲法上の解釈として伝統的にSTANDING(当事者適格)という概念が確立しているが、クラスアクションにおいても、いわゆる規制法違反がある場合に、法令違反行為だけではなく、実際に被害を被っているのか(INJURY IN FACT)を原告が証明すべきかどうかについて当事者適格の観点で争われたのが、SPOKEO事件である。事案は、さまざま個人情報を収集して提供するWEB事業(people search engine)を行っているSPOKEOというネットワーク事業者が、このような事業者は収集した情報が正確であるよう最大限の措置を講じる義務を負うことを定めた連邦法であるFAIR CREDIT REPORT ACT(公正信用報告法)に意図的に反して保有する情報が正確でなかったという理由で、FTCから罰金を課された。その後、一人の個人が、自分の個人情報として、氏名、年齢、職業、未婚既婚の別、趣味・嗜好等の広汎な個人情報が開示されたが、その情報はほとんど間違っているとの理由で、同様の被害を被っている被害者を代表してカリフォルニア州地方裁判所にクラスアクションを提起したが、同裁判所は憲法3条から導かれるINJURY IN FACTという要件を備えていないとの理由で棄却した。控訴審である第9巡回控訴裁判所は「制定法違反だけで通常は当事者適格(STANDING)として必要とされるINJURY IN FACTの要件を満たす」として、原告の主張を認めた。この案件は連邦最高裁に上告されたが、連邦最高裁は憲法(3条)に定める連邦の司法権に関する制約として、現実のケースまたは紛争の解決(cases and controversies of the sort traditionally amenable to, and resolved by, the judicial process) を前提とするという要件の解釈としては、原告は「実際に被害を被ったこと(suffered an INJURY IN FACT)」「対象となる被告の行為を証明できること」「司法救済が可能であること」を立証する必要があるとした。そのうえで、証明されるべき「INJURY IN FACT」とは、「具体的で特定された(CONCRETE AND PARTICULARIZED)法的な利益の侵害であって、現実かつ実際に発生していることを必要とし条件的または仮定的なものであってはならない」という従来の判例理論を示したうえで、本件においては「法令違反により本人の利益が害されたというだけで具体的にどういう被害が起きたかの立証がない」として、控訴審判決を破棄し、控訴審に差し戻し、被害の発生の具体性の有無についての再審理を求めたものである(SPOKEO,INC.,v. ROBBINS,136 S.Ct.1540(2016) )。この決定はクラスアクションに特有のものではなく、当事者適格の問題として被告が法令違反を行ったという事実では足りず、実際に原告に被害を与えたかどうかということを証明する必要があることを示したものといえるが、クラスアクションを含め、連邦の司法制度を利用できるかどうかという点で紛争解決に当たっての法的損害の具体性という根源的な問題を取り上げている点で、今後のクラスアクションの運用に大きな影響を与える可能性のある判決であるといわれている。
このように、成立要件とその前提問題を巡る攻防は、かつて相当緩やかに認められていたものについて、時代の変化により連邦最高裁レベルでは全体としてみると厳格化が進んできているといえる。しかし、州のレベルまたは連邦控訴審レベルでは、従来の実務にこだわる裁判所もあり、地域性や裁判官の特性を含め、弁護士の意見を聞きながら戦略を策定することが必要であろう。
⑹ クラス認定以降
クラス認定がなされた場合には、その内容、代表原告およびクラスの弁護士、クラスの範囲は、公告とともに、クラス構成員に知れわたるよう、最も適当な方法で通知(たとえば新聞の公告に加え、通知を郵送、メール等で送る)する義務があり、その費用は被告の負担となる。クラス構成員が代表原告、原告側弁護士が起こしたクラスアクションに拘束されることをよしとしない場合に備え、クラスアクションから離脱(オプトアウト)する機会を保障する必要がある。すなわち、離脱の意思表示をしないという不作為によってクラス認定及びその後の訴訟行為の効力は離脱の意思表示をしないクラスメンバーに自動的に及び、拘束することから、クラス構成員が確実に公告、通知を受けることはその判断の前提として必須の事項であるといわれる。
クラス認定以降の被告の防御方法は限られるが、その後にいわゆる本案に関するディスカバリーや専門家証人の証言が本格的に行われるが、実質面でクラスの範囲や賠償すべき損害を縮減したり、代表原告や原告側弁護士の報酬を抑制すべきことを主張したりすることで、被告として支出すべき総額を減らし、最終的な陪審の評決をできる限り有利に導くことに努めるか、和解を行うほかはない場合が多い。
(参考19)米国制度と日本法の制度の違い―成立要件対訴訟要件、立証責任
【BDTIについて】
役員研修は、実施している会社も多いとは言えず、研修内容も会社によって違います。まだまだ役員研修の分野は未発達です。会社役員育成機構(BDTI)では、各種セミナーに加え、会社法、金商法、CGコード、財務、ケーススタディなど役員として基本的な知識を身につけるための研修一日役員研修「国際ガバナンス塾」をはじめ、一日役員研修英語版のBoot Camp、役員だけでなく現場の方々にも基礎的な会社法やコーポレートガバナンスを理解していただくためのeラーニングなど多様な研修を行っています。