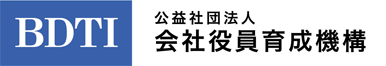外国法事務弁護士・米NY州弁護士 スティーブン・ギブンズ(Stephen Givens)
パナソニック・パナホームの完全子会社化取引
従来の買値が言われた通り正しければ、なぜその後20%引き上げたのか?
パナソニックは昨年12月、東京証券取引所1部に株式を上場する住宅事業子会社パナホーム(大阪府豊中市)を株式交換で完全子会社にすると発表した。ところが、今年4月、この株式交換の契約を解約し、代わりに、市場で株式を公開買い付け(TOB)することで完全子会社にすると発表した。これら発表が実現した場合にパナホームの一般株主が受け取る代金はそれぞれ大きく食い違っているが、それに関するパナソニックの説明はおよそ信用できない。これは、日本のコーポレートガバナンス(企業統治)の遅れを示している。
パナソニックは昨年12月の発表の後、「上場子会社」住宅メーカーのパナホームを完全子会社化するための株式交換提案の妥当性を繰り返し主張してきた。それらパナソニックの説明が本当に正しければ、4月になっての提案変更は必要なかったはずだ。しかし、パナソニックは提案を変更した。それまでパナホームが一般株主に説明した対価の計算と数値のどの部分がなぜ変わったのかを明確に説明することなく、パナソニックは対価を突然およそ20%(180億円相当)引き上げた。パナホームの株主にとっては、昨年暮れの提案より、ましな提案だと言えるが、パナソニックの株主にとってはどうだろうか。
パナソニックの株主は、当然のことながら「なぜ我々の財布から出る180億円分の値上げが本当に必要なのか?」についての説明を求めるだろうが、パナソニックの経営陣はその説明責任を十分果たしていない。パナソニック株主としては、パナホームをできるだけ安く100%子会社にしたい、と考えるのは当たり前だ。パナホームの一般株主は、原案より対価が20%も高くなり悪い気はしないだろうが、その反面、原案の説明が正しくなかったことが明白になり、その変更案を信頼するに足るか疑問を感じざるを得ない。その変更案の信頼性の担保がないからだ。
なぜこのような始末になったのか? 香港に拠点を置くアクティビストファンド「オアシス・マネジメント」はパナホームの一株主である(開示=筆者はオアシス側のアドバイザーを務めたことがある)。原案の発表以来、オアシスは
パナホームの一般株主にとってその値段は安すぎる、そしてその安値を承認した役員とファイナンシャル・アドバイザーの独立性と客観性は、大株主のパナソニックの影響を受けて歪んでいると主張してきた。オアシスの攻撃に対して、パナソニックとパナホームは、対価の妥当性と関係者の独立性・客観性を繰り返し訴えてきた。
しかし、日本企業の現状を考えると、独立性と客観性の主張はただの建前に過ぎない。パナソニックはパナホームの54%株主であり、実質的に密接な親子関係にあたる。パナホーム側の上層部が一般株主のために身内であるパナソニック側と激しく値上げ交渉することは想像しにくい。
密接な親子関係だけではなく、原案の作成と承認に係わった特別委員会のメンバー(主に会社側の弁護士や会計士にあたる者)、ファイナンシャル・アドバイザー(日本の大手証券会社)、そして、関与した法律事務所の実質的な独立性と客観性について、オアシスは問題視した。ファイナンシャル・タイムズ、日経新聞に批判的な記事が出た。安値を承認した「独立した」役員とアドバイザーのいずれもが、パナソニックを怒らせて、将来のパナソニックからの仕事の注文に影響が出ることを念頭に置いたはずだ。オアシスに対して、パナソニックとパナホームは、
特別委員会のメンバーとアドバイザーは法的には「独立した第三者」の定義に該当する、違法ではない
と主張したが、貧弱な形式論の域を出なかった。
これは推測に過ぎないが、パナソニックが最後まで外堀を埋める作戦でオアシスに対抗すると、会社のイメージに傷がつくリスク、またはパナホームの一般株主の大半が株主総会で完全子会社化取引に反対する可能性を考慮して、一歩譲歩した方が良いのではないか、という意見があり、4月の発表につながったのではないか。
さて、パナホームの一般株主に値上げを提供した方がリスクが小さいと判断した場合、パナソニックはそれについてどう説明するか? 原案を作成した人物には十分な独立性と客観性がやはりなかった、計算の方法論には欠陥があった、という説明はできない、ありえない。理由については、ぼやかす、ごまかすしかない。
実際、変更案の理由付けを読むと、無理を強く感じる。まず、パナソニックは完全子会社化取引の形式を株式交換からTOB(公開買い付け)に変えた。原案発表直後の税法の改正により、TOBの方が節税できるという説明がされている。しかし、節税の効果の具体的な規模(数億円?数十億円?)はどこにも説明されていない。節税効果があっても、180億円分の値上げに比べたらゴミのようなものでしかない。節税説は本当の理由ではない。
パナホーム側の説明も興味深い。アメリカでは法的に義務付けられているファイナンシャル・アドバイザーの「fairness opinion」(対価の妥当性を保証する正式な意見書)の不備があったとオアシスに指摘されたので、パナホームは、変更案の妥当性を裏付けるために正式な「fairness opinion」を用意した。しかし、新しいアドバイザーのレポートを読むと、パナホームの企業価値は4か月前の原案の時に比べて大分下がり、20%高い対価はパナホームの実際の企業価値をなぜか大きく上回ることになる。余分な対価をもらう側として、パナホームの一般株主は嬉しいかもしれないが、不合理な説明は喉に引っかかる。
さらに、パナソニック側の説明資料ではパナホームの新しい「fairness opinion」をそのまま引用して、原案の価格を20%つり上げることはパナホームの一般株主にとってフェアだと述べている。しかし、パナソニックの株主にとってフェアであるかどうか、専門家が計算したパナホームの企業価値を大きく上回る対価を払う必要があるかどうか、についての説明は抜けている。結局原案の建前を守るために、変更案も不信感を起こさせる作りになってしまっている。嘘を一ついえば、元の嘘を守るために、その後際限なく嘘をつかなければならなくなってしまうのだ。
ソフトバンクとヤフー、日立グループ、NTTとNTTドコモのような「親子上場会社」関係は利益相反関係を甘く考える日本人には馴染みやすい現象だ。しかし、日本企業のコーポレートガバナンスをグローバル・スタンダードに上げていくために、「親子上場会社」は厄介である。上場子会社の多数株主である「親会社」と、少数株主である一般株主の間に利害が対立する危険はおおいにある。事実として、上場子会社のROE(株主資本利益率)やPBR(株価純資産倍率)は平均よりはるかに低い。その原因は、親子間の取引の条件は親側に有利に設定されていて、子会社には最低限の利益だけを残す仕組みになっているからと推測される。
日本企業は親子上場会社の厄介な利益相反問題を意識するようになり、パナソニックによるパナホーム完全子会社化の提案はその問題を解決するための手段である。完全子会社化は明らかに望ましい。しかし、完全子会社化を実行する段階になると、構造上の親会社と一般株主の利益相反が顕著になる。親は一般株主の株を安く買い取りたい、一般株主は反対に高く売りたい。親は子の多数株主である立場から、子会社、そして子会社の経営陣を操ることができる。完全子会社化を実行する取引は必然的に利益相反だらけだ。
アメリカと日本の完全子会社化取引(going private transactions)のルールと実務を比較すると、アメリカの方には少数株主を色々な観点から保護するという特徴がある。例えば、日本と違って、アメリカの上場会社の取締役会の半分以上は独立した社外取締役でなければならない。アメリカでパナソニックのような大企業のgoing private transactionを評価する特別委員会は、2-3人の弁護士や会計士ではなく、利害関係がなく独立性が明白な同等規模の企業のトップ経営陣5-6人が務める。しかも、特別委員会のファイナンシャル・アドバイザーと法律事務所は、会社側と常に継続的な関係を持つファームではなく、一時的にその取引だけのために採用されるケースが多い。また、親が買い取ろうとする子会社をオークション(競り)に出すことが基本的に義務付けられていて、親子間の一対一の「交渉」で条件が決まることはまずない。そして、少数株主が価格について不満があれば裁判所に決定を委ねることは日本と同じだが、アメリカの裁判所が適用する判断基準は日本に比べてかなり厳しい。
日本におけるコーポ―レート・ガバナンスのルールは大分グローバル・スタンダードに近づいてきたが、完全子会社化取引を巡る少数株主の法的保護はまだグローバル・スタンダードとは大きな隔たりがある。この隔たりを縮めるために、日本に馴染まない物事の決め方――具体的に重要事項を第三者の判断に委ねるルール――を会社に導入する必要がある。それを実現するためには、最終的に会社法の改正も必要になるだろう。いずれにせよ、パナソニックのように現状のルールを最低限守ることにとどまると、常識的な意味の「独立した」判断で対価が決まったと言えなくなる。現状の日本の制度は嘘を招きやすく、企業に対する信頼を損なう危険性をはらんでいる。
スティーブン・ギブンズ
▽AJ編集部による注付きのリンク: