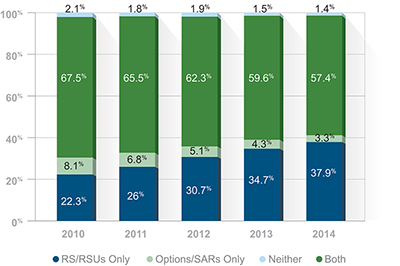ISSの次に世界最大の議決権行使助言会社Glass Lewisが2016年版の議決権行使助言方針を発表した。日本語版の方針を発表したのは初めてである。
投稿者: Admin
Glass Lewis Issues Proxy Voting “Policy Guidelines” for Japan,…in Japanese
Glass Lewis has issued is policy guidelines for 2016 for the Japanese market, in both English and Japanese. It is a statement of the times that Glass Lewis made a Japanese translation this year, as they have not done that in previous years. Against the backdrop of recent reform, the policy guidelines may be seen as a bit meek for case of kansayaku-style companies, although some of the provisions clearly reflect the fact that a Corporate Governance Code is now in effect.
証券保管振替機構など:「株主から剰余金の配当に関する提案が行われた場合の標準モデル」
「剰余金の配当(以下「配当」という。)の支払いに係る現行実務は、会社提案の配当議案が株主総会で可決されることを前提に、関係者が株主総会決議前から配当金支払事務を開始することにより成り立っており、配当に関する株主提案が行われ、当該提案が株主総会で可決される場合には対応できない仕組みである(取締役会決議で配当をすることができる旨の定款規定がない場合に限る。)。
3/3 BDTI Seminar: “Global Trends in Antitrust Enforcement: What the Future Holds”

Japan’s Antimonopoly Act (the AMA) was recently amended so as to adopt a wider and deeper scope for the surcharge system, a leniency program, and the authority to investigate criminal cases as measures to strengthen enforcement.
”Proposals for Raising Productivity in Japan” (by Nicholas Benes)
 Proposals for Raising Productivity
Proposals for Raising Productivity
This is an English translation of a presentation in Japanese that I have given recently to several influential members of the government.
The opinions are my own.
2016.04.27 みずほ総合研究所主催:「コーポレートガバナンス・コード」フォローアップセミナー
 BDTI代表理事 ニコラス・ベネシュが講師を務める、「コーポレートガバナンス・コード」フォローアップセミナーが4月27日(水)13:00~17:00 みずほ総合研究所 セミナールームにて開催されます。
BDTI代表理事 ニコラス・ベネシュが講師を務める、「コーポレートガバナンス・コード」フォローアップセミナーが4月27日(水)13:00~17:00 みずほ総合研究所 セミナールームにて開催されます。
コーポレートガバナンス・コード(以下CGコード)が上場企業に適用され、もうすぐ1年が経ちます。開示資料を提出して一通りの対応を終えた企業でも、「自社のComply、Explain の線引きは本当に正しかったか?」「このExplain で十分だろうか?」「こんな抽象的な表現でも株主は納得するのか?」といった疑問は残っていませんでしょうか。
また1年目は「検討中」としていた部分も、2年目を迎える今、株主総会を前にしてどのような質問が来るのか不安はありませんでしょうか。本講座では、コードの提唱者であるニコラス・ベネシュ氏と当社の実力派コンサルタントがタッグを組み、各社がベストプラクティスを導くためのヒントを豊富にお伝えします。
コード本来の目的を再確認した上で、ガバナンス報告書をもとにした企業の対応状況分析、情報開示の「質」についての検証、さらに株主が重要視する項目については実例を点検し、具体的な改善策の呈示を行います。
また講義では、今後のコード改訂対象になり得る項目・内容、および投資家が何を期待するか、についても解説します。
PB Analytics – Japanese Boards, Composition at FYE

Excerpt: As of the last full year end for the 3,678 companies in the PacificData database, there were 4,267 Independent Directors or 10.6% of the total number of Directors. The total number of female Directors was just 966 or 2.4% of the total – well below even the 9.5% ratio of female members of Japan’s House of Representatives.
2016.04.04 会社役員育成機構(BDTI)セミナー『「対話」の時代、株主総会とIRはどう変わるか? ~国際的な視点から~』

規制環境の変化と技術の進展により「株主総会」の参加方法と役割が変わりつつあります。海外ではインターネット配信だけではなく、インターネットによる対話システムの利用およびバーチャルの株主総会が増えています。
KPMGジャパン:「株主との対話-コーポレートガバナンスとIR/SR活動の今後」
「一連のコーポレートガバナンス改革が想定している投資家は機関投資家です。
アベノミクス相場の元において日本株は顕著に推移していますが、その背景にあるのがそれら機関投資家による買い増しです。
メディアでは、ここ数年株価を牽引してきたのは、外国人と国内公的年金による買い増しであると報じられてきました。それ自体は間違いではありませんが、実態はやや異なります。実際に日本株に投資している機関投資家の属性に着目すると、日本株の買い主体はパッシブであり、長期的観点から企業価値を評価する投資家ではない、という一面が見えてきます。また、これは「資本コストの低減を通じた企業価値の顕在化」を目指すIR/SRにおいても、その実現の難しさを浮き彫りにしているといえます。