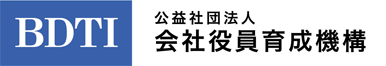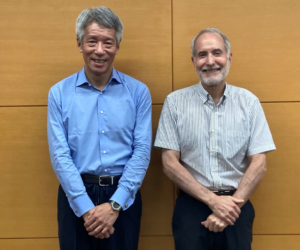
● 公認会計士であることが自身の視野や行動を狭める要因
小林 公認会計士が社外役員として就任するケースが最近になって非常に多くなってきています。その際に、どのようなスキルやマインドセットが必要なのか、リアルなガバナンスの現場をご存じであるベネシュ氏にお話を伺いたいと思っています。
ベネシュ 一個人の公認会計士としてならば、アイディアやアドバイスを顧客企業に提供することに問題はありません。しかし、公認会計士たる社外役員には独立性が求められているため、就任先の企業に対して、いざという時は辞める覚悟で、たとえ企業の経営陣にとって不利なことでも発言することができないのであれば真の役割を果たせたとはいえないと思っています。

小林 私は、公認会計士の独立性が非常に重要だと考えているのですが、組織人になってしまっている人もいる感覚がありま す。いざとなったら私は辞めても良いという気概で社外役員になることは本当に必要ですし、求められていると思います。その点に関して、企業側と社外役員側、双方の感覚の違いなどについてどうお考えですか。
ベネシュ 社外役員を指名するのは事実上執行サイドの役員がほとんどです。これを「顧客企業」からの依頼だと認識してしまう公認会計士もいるように思われます。結果として、執行サイドのトップである社長の考え方に無意識のうちに同調してしまうのでしょう。一方で、少数株主の代弁者だと自覚している人も少なくはありません が、よほどの事件が起こらない限り企業の戦略や人材マネジメントなどに関する社長と経営陣の意見について反対するコメントはなく、自分の役割を狭め広く見ることができていない場合もあるようです。
小林 今のお話について言えば、企業から公認会計士の知見を重視して社外役員に選ばれているのだと本人が解釈すると、自分の発言の内容をその部分に制約してしまう傾向があるのかもしれません。自分の分野で発言すれば良い、役割を果たせば良いと思い込んでいる可能性がある。会社の全てにわたる監視・監督という社外役員の責務に関する意識が抜け落ちてしまっているということでしょうか。
ベネシュ 公認会計士は会社経営に関わる制度的な枠組みに関する知識を持っています。しかしながら、全ての公認会計士が自身で会社をマネジメントした経験を有しているわけではありません。豊富な知識があるがゆえに会社の様々な側面、分野を理解していると誤解してしまうのではないでしょうか。内部統制や財務諸表の理解などガバナンスに関連性があるトピックに頻繁に携わってきたため、十分な知識があるという考えを持ってしまう人もいるかもしれません。社外役員という仕事は終わりなき旅です。常に勉強をしていくという自覚を持つべきしょう。
● 経営側に都合のよい状況から脱却できない日本の体質
ベネシュ 指名委員会、「任意」の人事諮問委員会などが頻繁に行われる傾向にありますが、意味のある話し合いをしているのは全体の 2 割程度でしょう。ほとんどの会議の場に常にメンバーとして社長が入っているのが問題だと思います。これでは顧客企業の代弁者ばかりを集めた話し合いになってしまう。極端な発言かもしれません が、社長は指名委員会のメンバーになる必要はありません。専務取締役やマーケティングの専門家など内部の人から意見を聞く際に、「社長がいるから言えない」という会議は機能していると言えないでしょう。
小林 これは社外役員のマインドセットにも原因があるような気がしますが、一方では会社側のガバナンスに対する意識がまだ一定のレベルに達していないということとも考えられます。つまり取締役会の中で、無難な発言しかしない人ばかりを選んでしまっているのでしょう。
ベネシュ 現時点で日本のプライム市場では、取締役の平均的な数は 9~10 人ぐらいで、そのうち 4 人は社外取締役です。元経営経験者 2 人、弁護士 1 人、公認会計士 1 人という構成が多く、統計的には社外取締役の 6 割くらいが経営の経験者です。
この経営者たちの多くは失われた 30 年間で非常につらい経験をし、なるべくリスクを避けよう、低減させようと頑張ってきた人たちです。また、若い人の積極的な登用がないことも心配です。例えば海外経験やインターネット関連業界の経験が豊富な若い世代はたくさんいます。しかし、新しい時代の人的資本が経営の中枢に参加できていません。兼務の禁止がそれを阻んでいると考えています。海外でしたら、GE のトップを、別会社の社外取締役として就任させるケースもあり得るのです。
小林 日本でもそのような取組が必要だと思います。日本の取締役会の構成を見る と、最近は執行側が若くなってきてはいますが、社外取締役の年齢が、執行側の取締役よりも平均 10~20 歳も高いという傾向がありがちになってきているのも大きな問題です。
ベネシュ 米国では 60~65 歳以上ですと、なかなか社外取締役の候補として検討してもらえません。良い社外取締役であれば 10 年以上でも務めてほしいと考えているためです。一方で、日本の取締役会の背景にあるのは暗黙の任期です。社長に就いて 5~6 年、社外取締役は 4~5 年、長くても 7 年。何となく掛け持ちして次の会社へ転々と渡り歩きます。私の感覚ですが、一つの会社をよく知ると言えるのは 2 年目以降です。その頃からより意味ある貢献ができるようになります。そう考えると、経営陣にとって「4~5 年でいなくなる社外取締役の方が都合が良い」という思惑が背景にあるのかもしれません。
小林 ようやく会社の内情が分かった頃に任期となり、何もできずにお終いとなってしまうわけですね。つまり、耳の痛いような批判や指摘をすることを歓迎するか、早くいなくなってほしいと考えるかは経営陣次第なのでしょう。
ベネシュ ガバナンスの質を語るというのはそういうことだと考えています。妥当な指摘をされたときに謙虚にそれを受け止める。そして、自分の責務を一生懸命に全うしようとしている社外役員を尊重するという心構えが経営陣側にあるかどうかなのです。
● 経営会議の承認の場となり、形骸化してしまう取締役会
ベネシュ 日本の15年前を思い返してみると、経営陣の取締役会に対する目的は「とにかく早く終わらせること」でした。誰かが月次数字を10~15分ぐらいかけて棒読みする形式的なもので、経営会議の資料がそのまま取締役会の資料に流用される。当時のガバナンスに対する考え方が日本にはいまだに残っているようです。
小林 執行側はすでに経営会議で資料を見ていて、その内容を取締役会に上程して承認してもらうという、経営会議の延長に近い儀式のような取締役会になってしまっている会社もあると聞きます。
ベネシュ 経営会議と取締役会、この二つは異なる目的と役割を持った会議です。経営会議に使った資料を取締役会の資料として添付しても構いませんが、それは事前に読むことができます。取締役会は経営会議で議論されたことに判を押してもらう場ではありません。経営会議で見逃した点を洗い出し、問題提起をしたり、新しいアイディアを捻出したりするための会議です。そういうマインドセットを育てていくべきです。
小林 取締役会がこのように儀式的なものになってしまうと、社外役員は上程された議案に対する査閲機関のようなどちらかというとストッパー的な存在になり、アクセルを踏む役割を果たさなくなる気がします。社外役員について言えば、何を発言すればよいか分からず、自分の専門分野で何か発言してお茶を濁しておけば良いと考えてしまうケースもあるでしょう。
ベネシュ ある企業の取締役会にもう16年間ほど参加してきた経験でいうと、活発に発言する社外取締役のパーセントが上がれば上がるほど、その他の取締役は議題に参加して発言したくなる、貢献したくなるという傾向があります。自分だけ蚊帳の外になりたくないというプレッシャーを感じるのかもしれません。例えば社外役員が2人しかいない場合と6人の場合、後者の方が明らかに会議のクオリティが向上します。
小林 自然に競争意識が芽生えるということでしょうか。他の人が何か発言して貢献していると、自分も貢献しなければいけないと自尊心が刺激され、良い影響をもたらされるのですね。
● ガバナンスの変化で社外役員に求められるスキルが変わる
ベネシュ プライム市場では3分の1以上が社外取締役であることが原則になるようですが、次の改訂ではおそらく過半数の独立社外取締役にシフトすると思っています。すでに現在のプライム市場の2割近い企業は、過半数の社外取締役という条件を満たしているのです。こうなると、まず取締役会のパワーバランスががらりと変わります。社長が議長を兼務することがなくなり、独立社外取締役が議長になるケースが増えるでしょう。また、公認会計士1人、弁護士1人に加えて、経営経験者という構成が変化し多彩な経歴の社外取締役が加わってくる。AIの専門家や、人事関係のプロ、ITや企業戦略のコンサルタントなども候補になります。インドなどの海外市場に精通した外国人経営者なども良いでしょう。これにより、取締役会の議論は今以上に活性化して、有資格者である公認会計士も自分の専門分野以外のトピックスに対しても発言しやすくなります。一方で、戦略論や組織論、ITに関する知識などを身につけていないと、競争の中で勝ち残れません。公認会計士として今のポジションのままならば、いずれ置いていかれることになるでしょう。
小林 現在は、この発言をしても良いのだろうかとか、少し臆病になりながら発言をするケースもあると思います。しかし、取締役会で活発な意見交換が生まれるようになるためには、従来の社外役員が今のままで良いはずはありません。もっと自分の専門分野以外のことについても勉強しなければなりません。そのような意味では取締役会の出席者に刺激を与えるためにも多彩なキャリアの社外役員の参加は重要だと思います。
ベネシュ 社外取締役の仕事の3分の2以上は質問をすることだと私は思っています。経営陣が十分に分析して、様々な選択肢を考えて、それを比較する。そこに何か失敗になる要因はないか、どういうリスクがあるか、何か起きたらどう対応するかということを問題提起するのが役割です。
その際、公認会計士たる社外役員について考えると、専門家という意識や自負は足かせになるかもしれません。専門的知識を持っていなければ価値がない、この話題には参加しないほうが良いという間違った謙虚さは怠慢だと評価される場合もある時代なのです。
●社外役員の動きが取締役会を健全な方向へリードする
ベネシュ 米国も10年前ぐらいまでは、ほとんどの会社で社長が取締役会の議長を兼務していました。しかし、社外取締役たちがどのような課題について心配しているか、どのようなトピックの議論をしたいのか、という意見を集めて議題に乗せるよう促す筆頭社外取締役が準議長のような役割を果たしていたのです。やがて社長ではなく社外取締役が議長を務めるという動きになっていきました。米国の場合は6~7割は独立議長又は筆頭社外取締役が取締役会を健全な方向へとリードしています。CEOが議長を兼務するのは45%以下です。
小林 これは大変興味深いお話だと思います。日本の会社では執行側が取締役会に上程する議案を決め、それを議長がある意味セレモニー的に進めていくような取締役会が多いのではないかという印象です。筆頭社外取締役といったような役割をつくり、議案上程のプロセスにもっと関わっていかなければならないと感じます。
ベネシュ これは社外取締役の態度によって変わるものですので、社外役員側の責任もあるとは思います。執行部が将来このようなことを計画している、このようなことを検討中、分析中などの情報を報告してくれる会社も実際にはあるのです。これは健全であり、自然に良い流れの議論になっていきます。
小林 そのような意味で考えると、取締役会にこだわらずオフサイトで何かするというアイディアも考えられます。社外取締役がもっと活発に動き、そのような場の形成を要求していくのも一つの方法だと思います。
ベネシュ 企業価値を考える場合、それを一番欲しがっているのは株主です。市場が何を期待しているか、何が株価にインパクトをもたらすかなど、株主が気になっていることに関する発言が、日本の取締役会ではあまりにも少な過ぎる気がします。社外役員の皆さんには、資本市場のダイナミクスやコモンセンス、投資家はどう見ているかという感性、そのようなものをもっと養ってほしいと思います。
● 日本の取締役会にはないボードリーダーシップの概念
ベネシュ 海外では「ボードリーダーシップ」という言葉があります。これは取締役会で社外取締役が過半数を満たした状況 で、必要に応じて大胆に取締役会をコントロールすることです。その意に沿わない社長を交代させることもできますし、社長以外にもう 1 人別な人間を立てて戦略の再検討の場を調整することもできます。これは社外取締役間の信頼関係がなければ成立しません。海外では社外取締役は株主に承認していただく存在であるという意識が高いです。そのため、何か問題になったときには指名委員会が株主に配慮して彼らを再指名しないという可能性があるのです。「あのボードは何をしていたのか」ということを気にしているからなのです。そのような力が働いているからこそのボードリーダーシップです。
小林 日本ではそういうものがあるということすら認識されていないように感じま す。取締役が個別に何をしてどのくらい貢献したのか、その貢献に対する評価はどのくらいか。そのような話題はとても難しいトピックであり、あまり表に出ることもありません。どちらかというと社外役員はお客様扱いされ、ある意味、名誉職のような印象です。特に公認会計士がプライム市場の会社で社外取締役となる場合、監査法人で長らく勤務してきた方が何社かの社外役員でそのように扱われてしまうというケースがあるように思います。
ベネシュ 数社を兼務している社外取締役は、戦略上の大きな M&A があったときや不祥事が起きたときに、本当に 1 社に注力して対応できるのか心配です。十分に対応できなければ、最終的にその社外取締役は責任を問われることになりかねません。
● 公認会計士のスキルへの期待感
小林 スキルマトリックスの開示において、公認会計士は会計に加えて財務、いわゆるファイナンスのスキルをセットとして持つとされているケースが多く見られま す。そのようなイメージで見られているということは理解できますが、会計とファイナンスの観点は大きく異なっている部分もあり、イメージと現実の間にはギャップがあるのではないかと感じることがありま す。これは結構大きな課題だと思っています。
ベネシュ 確かに会計はファイナンスと違います。ファイナンスを知っていると言えるために又は使いこなすために、会計についてのある程度の知識は必要です。しか し、詳しい IFRS のルールを知らなくてもその数字が何を意味しているかということは理解できるはずです。
小林 公認会計士が監査意見を表明するときには、ゴーイング・コンサーン注記がついてしまうことを嫌がる気持ちがあると思います。こういった傾向を持つ公認会計士が社外役員に就任した場合、監査人と同様の視点で、その会社がキャッシュを潤沢に保有しているということが良いことだと評価してしまうのではないでしょうか。企業のゴーイング・コンサーンを重視した経営と資本コストを意識した経営の間には微妙な対立とバランスの関係があります。公認会計士がそれを理解して社外取締役に就いているか疑問に思うことがあります。
ベネシュ 経営においてはキャッシュを持っていれば良いという訳でなく、それを何に使うのかということが重視されます。ビジョンを持って投資できる R&D などのプランを持っていなければ、潤沢な資金があっても株主は納得しないでしょう。もし大きな投資をしないのであれば、残す現金はどれぐらいか、運転資金はどれくらいで安全性が保てるかなど、ファイナンス的な視点での裏付けが必要になります。
小林 最近アクティビストが様々な企業に対して、場合によっては新聞に広告を打って株主として経営側へ説明を要求してきます。彼らの行動を見ていると、よく研究していますし、取締役会の中でもこのような議論がされるべきだと感じました。彼らの活動から学ぶべきところは非常に多いような気がするのです。
ベネシュ アクティビストの手段に賛同できなくても、彼らが言っている内容の 7 割強は評価できると感じています。もしアクティビストが提言してきたとしたら、友人として歓迎するよう経営陣にはアドバイスしています。オープンマインドで聞く耳を持ち、最初からノーとはねつけるようなスタンスを取ってはいけません。彼らの多くは株式を意外に長期保有している株主でもあるわけですから謙虚に接するべきです し、多くの学びが得られると思っています。
● 事象を定量化できる公認会計士のスキルは大きな強み
小林 日本の企業は市場から直接資金を調達するのではなく、銀行からお金を借りるという間接金融の時代が長らく続いてきました。つまり海外に比べ市場と向き合うマインドセットになっていないのです。銀行は投資家というより債権者ですので、回収の安全性を求めます。そのため日本ではリスクを取らずにとにかく安全性を意識することが、経営者にも監査人にも根づいてしまっているように感じます。
ベネシュ 米国の場合、上場企業の約半分は利益を出していません。短期的に利益を出してない会社は日本では良くない会社とされ、経営陣は利益を出さないのは恥だと考え、株主からは批判を受けてしまいま す。しかし海外ではビジョンを持ちそれをストーリーとして投資家にアピールできるのであれば、短期的には営業利益がなくても構わないと受けとめられます。中長期的な視点でダイナミックな資本市場に変わることが目標なのです。しかし日本ではなかなかそのようにはなりません。
小林 ABC による成績評価でいえば、常にB ぐらいは取っておいてくださいという考え方ですね。絶対に C やD にはなってはいけないというイメージです。短期的に下振れてしまうということに対しての嫌悪感が経営者側にあり、日本の市場もそう受けとめている気がします。
ベネシュ 海外の場合は半分以上、米国では 3 分の 2 以上が、経営陣の報酬は株式です。譲渡制限付株式などが多く、社外取締役も株価に連動した報酬を受けています。そのおかげで、経営陣は自然にリスクテイクする仕組みになっています。株式による報酬を受けるメリットは、取締役会の視線が株主の期待に重点を置くようになることです。したがって社内から積極的に良いアイディアが上がってきます。自分たちの利益も株価にかかっているわけですから、競合他社との関係でどのように優位性を保てるか、どのぐらいのマーケットシェアを取れるかなど、経営者は十分に分析をした上でリスクを負って投資するのです。
小林 リスクテイクという面で考えると、公認会計士は少なくとも様々な事象を定量化して数値で表すというスキルに優れていますので活躍の場があるはずです。つまりリスクを定性的に見てしまい感情的にネガティブになるのではなく、定量的に分析して数値で経営判断できるように持っていけるのではないでしょうか。そのようなスキルは、公認会計士ならではのものだと思います。
ベネシュ 確かにリスクの分布を統計的に定量化した分析や様々な選択肢を提示することで、否定的なリスクに直面した状況でも投資を拡大したほうが良いという論理的な判断ができる可能性は高いでしょう。
● 社外役員は自身を常にアップデートしていくことが宿命
ベネシュ 2013 年に私が政府に提唱した後、日本ではコーポレートガバナンス・コードが 2015 年に導入されました。しかし、これが本当の意味で機能するにはまだまだ時間がかかりそうです。分析に基づいてビジョンを描く、具体的にそれを実現するためのストラテジーを作成する。しか し、そのような分析が経営者からなかなか上がってこないのが日本企業の根本的な問題です。言うのは簡単だけれども行うのは難しいのです。
小林 そのような状況を鑑みると、公認会計士たる社外役員は専門分野だけでなくあらゆるトピックに対して積極的に発言していくことが求められます。「自分は十分に知っているのだ」という考えではなく、「知らないことがまだまだたくさんある」という姿勢で勉強するべきだと考えています。
ベネシュ これは公認会計士だけに言えることではありません。社外役員は常に勉強して自身をアップデートしていかなければならないのです。制度的な枠組みの一端をよく知っている専門家だからといって、取締役会メンバーのエキスパートではありません。公認会計士には志が高く優秀な方が多くいると思っていますので、自己研鑽を重ねれば必ず貢献できると期待していま す。社外役員は顧客企業にアドバイスやアイディアを発言しているわけではなく、少数株主や投資家の期待を担っているという点を忘れないでください。
<対談者経歴>
ニコラス・ベネシュ(公益社団法人会社役員育成機構(BDTI)代表理事):
J.P.モルガンにて 11 年間勤務後、M&A アドバイザリー業務に特化する株式会社J TPを創設した。米国カリフォルニア州及 びニューヨーク州における弁護士資格取得。2013 年、金融庁主導の「コーポレートガバナンス・コード」制定の提案者として、担 当議員及び金融庁にコード内容に関して詳 しく助言。現在、アドバンテスト社(証券 コード:6857)の独立取締役を務める。
対談はこちらからダウンロードできます。
出典:日本公認会計士協会公表物から転載