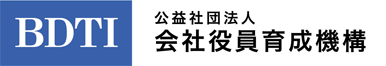強圧性のある買収には買収防衛策で対抗する必要がある、ないし対抗することが許容される、という考え方がある。しかし「強圧性」とは何か、必ずしも明らかではない。「強圧性がある買収は良くないと言われるが、何が強圧性のある買収なのか、様々な指摘がある」とするのは、経産省で開催された「公正な買収の在り方に関する研究会」第1回2022年11月18日冒頭における事務局説明である。
「強圧性」はかなり広い概念である。「企業買収と防衛策」(田中亘著商事法務初版第2刷2013年3月10日)によれば、「対象会社の株主が買収に応じないでいる間に買収が実現すると、その株主は、買収に応じた場合と比べて不利益を被ると予想されるために、株主が買収に応じるような圧力を受ける場合、その買収手法には、強圧性がある」。このようなものが「強圧性」と考えると、買収者が支配権を獲得した場合には、不利益な取扱いを受けることになってしまうのでは、と株主には一抹の不安がよぎるだろうから、いつでも「強圧性」の問題があることになってしまう。
しかし、「企業買収法の課題」(飯田秀総著有斐閣2022年12月20日)によれば、「強圧性の問題は、強圧性があることそれ自体が問題なのではなく、企業価値を減少させる好ましくない企業買収ですら強圧性を利用すると成立してしまうことが問題である」。買収が実現した後の対象会社の企業価値が買収前の企業価値よりも低くなると予想される、つまり成立させない方が良い買収の場合に、企業価値を減少させる買収であるということ自体が理由となって、むしろ買収が成立しやすくなるのが、問題の本質である。
「強圧性」には「実質的強圧性」と「構造的強圧性」とがある。「実質的強圧性」とは、「公正な買収の在り方に関する研究会」第4回2023年1月26日事務局説明資料によれば、「企業価値を損なう買収提案であるにもかかわらず株主が十分な情報がないままに誤信して買収に応じてしまうおそれ」とされる。これに対し、「構造的強圧性」とは、「取引の構造上、対象会社の株主が買収に応じないでいる間に買収が実現すると、買収に応じた場合と比較して不利益を被ると予想される場合には、たとえ多くの株主が買付価格は客観的な株式価値より低いと考えている場合であっても、株主が買収に応じるような圧力を受けるという問題」とされている。
そこで、買収の手法(構造)に目を向けると、買収にはいくつかの手法がある。まず市場内で株式を買い集める場合にも「強圧性」はある。買収が成功して、買収者が支配権を獲得すると、企業価値は下がるのだから、早い者勝ちで売ってしまおう、ということになる。「企業買収法の課題」(飯田秀総著有斐閣2022年12月20日)によれば、市場買い集めには情報開示が少なく、「市場買い集めがいつ始まっていつ終わるのかが不明であるため、対象会社の株主としては売却できるうちに急いで売却しておこうという行動をとりがちであり、強圧性の問題は市場買い集めの場合はより深刻とすら言える。」
もちろん、公開買付にも「強圧性」がある。公開買付の中でも、一番問題があるのは、強圧的二段階買収というもので、「公正な買収の在り方に関する研究会」第4回2023年1月26日事務局説明資料によれば、「最初の買付条件を有利に、二段階目の買付条件を不利に設定する、あるいは明確にしないで行う買収(強圧的二段階買収)については、強度の強圧性が指摘されている。通常、買収防衛策の発動要件とされている。」と評されるものである。逆に、低減のために工夫を施したAll or nothing offerというものは、強圧性が低いとされている。これは、同資料によれば「上限を設定せず(全部買付け)、買付後の株券等所有割合が3分の2となるように下限を設定し、公開買付け成立後に公開買付価格と同額でキャッシュ・アウトを行うことを予告する二段階買収」である。現実の世界では、これら両極端の手法の間に、上限と下限の設定の仕方、買付後の計画の公表の有無・内容を組み合わせて、様々なバラエティーがある。
支配権獲得には一定の株式数(例えば50%とか67%とか)が必要なので、公開買付には下限を付けるのが、本筋ではある(そうでないことも多い)。下限を下回る応募しかなかった場合は、公開買付は不成立となり1株も買い取られることはない。他方で、上限をつけるかどうかが、全部買付、部分買付の区別である。応募株式全部を買い取るのが全部買付だが、部分買付の場合は、上限を上回る応募があった場合でも、買収者は上限までしか買い取らず、応募者は按分比例により応募株式の一定割合しか売却することができない。
上限を付ける部分買付の方が問題が大きいとされている。買収者は支配権獲得を目指しているので、(例えば)50%は欲しいが、逆を言えば50%で良い。だから上限も下限も50%という公開買付を行う。この条件設定は、「企業買収法の課題」(飯田秀総著有斐閣2022年12月20日)18頁と同じである。しかし同頁が使用する、数値例(株式の時価2600円、買付価格3000円、買収が成功した場合の予想株価2200円など、三つについて数値例を示すもの)は使わずに、ここでは、言語で感覚に訴えてみたい。
ある株主は買収者が支配権を獲得したら株式価値が時価より下がると思うので、買収は失敗して欲しいと考えている。しかし、他の株主がどうするかが分からない。自分以外にも多くの株主がいることを踏まえ、個々の株主がどう行動するかに、買収の成否はかかっている。個々の株主はまさか自分がキャスティングボートを握っているとは思っていない。そして、部分買付であるから、買収者は、少ない株式を購入すれば済むので、単価は上げられる(高いプレミアムがつけられる)から、買付価格は魅力的に設定できる、というのがミソである。
結果論から遡って考えてみる。結果として、①50%以上の株主が応募した場合には、ある株主は企業価値が低くなる会社に取り残されないよう、応募すべきであったということになる。上限がついているので、応募しても全部を買い取ってもらえるわけではなく、他の株主と按分比例されてしまうわけだが、それでも全分を取り残されるよりマシである。逆に、結果論として、②50%未満の株主しか応募しなかった場合には、買収は実現しないのであるから、ある株主が応募すべきだったかどうかは無意味であり、応募しておいても別に悪くはなかった、ということになる。すると、両方の場合を合わせてみれば、応募しておけば良い、ということになってしまう。この論理は、全ての株主に当てはまるので、全ての株主が応募し、その結果として買収は成立し、対象会社の企業価値は低下してしまう。
部分買付と比較すれば小さいながら、全部買付にも「強圧性」の問題はあるとされる。応募株は全部買い取るのだが、下限50%の条件はついている場合、買収の成否はやはり多数の株主の動向により決まる。結果論から遡ると、買収成功失敗どちらの場合でも、個々の株主とすると応募しておけば良い、と理論が成立するのは、上述した部分買付の場合と同じである。だから強圧性はある。
ただ、全部買付の場合には、買収者としては多数の株式を購入する必要があるので、単価は下げる必要があり(プレミアムは低い)、買付価格は低い。このため、②50%未満の株主しか応募しなかった場合が実現する確率が高くなり、個々の株主は、場合にもよるが、それを予測、確信できるようになる。他の株主も応募しないなら、企業価値を低下させる買収を成功させるようなことは自らしたくない。だから応募しない。他の株主も同様に考えるから、買収は成功しない。こう考えると、全部買付にも強圧性はあるものの、部分買付ほどではない。
このように「強圧性」はそこここに存在する。そして程度に差がある。一番程度の高い(問題の大きい)強圧的二段階買収から、低減のために工夫を施したAll or nothing offerのようなものまで、様々である。その程度によって買収防衛策の導入・発動が許容されたり、求められたり、問題視されたりする。独立社外取締役にとって、「強圧性」の基礎を理解しておくことは、いざというときに、非常に大きな財産となるだろう。