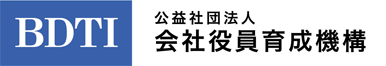とても参考になりますが、下記の点について、実はドイツだは組合代表者が監査役会の半分を占める法律を作ったのは、戦争後に占領していたイギリス軍でありました。また、日本はより「ステイクホルダー主義に基づくエクイティガバナンス」を貫くのであれば、一時退職金に現金積立を義務付けて、企業年金の積立率を100%にすることからはじめればいいと思われます、、、。

「著者がガバナンス改革のお手本としているのは、ドイツである。1999年には日本とドイツのGDPの差は2倍だったが、今では2割程度に縮まっている。それはシュレーダー政権の改革による成果であり、その柱の一つがコーポレートガバナンス改革であった。
では、なぜコーポレートガバナンスが、企業の稼ぐ力につながるのだろうか。それはガバナンスによって「経営陣の不作為の暴走」を止めることが可能だからだという。90年代以降の日本企業は、経営者や経営陣が必要なリスクを取らず、非連続な成長を極端に嫌った。その結果として、長期にわたり低成長、低収益に甘んじてきたと分析する。ドイツのガバナンス改革はここにメスを入れて、稼ぐ力を回復した。
ちなみに、日本企業は上部構造の企業経営に問題がある半面、現場力(主に、製造や開発の現場)は衰えておらず、今でも強い。それはドイツも同じであった。そのため、本書は「日本企業の現場力は強いので、経営陣を外から規律付けるガバナンスを強化して上部構造を改革すれば、日本企業もドイツ企業のように稼ぐ力を高められる」という前提に立っている。
論理はその通りだが、実際に改革するのは簡単ではないだろう。その最大の理由は、ガバナンス不全が起きている原因が、ガバナンス制度の不備だけではないからである。実際、昨今の東芝の不正会計はコーポレートガバナンスの体制に特段の不備はなかった。だから、形だけを整えれば何とかなるというわけでなない。日本企業のガバナンス不全の最大の原因は、多くの日本企業が「サラリーマン共同体至上主義」であり、ムラ社会的な「空気」が組織を支配していることにある。これは本書も指摘している点だ。
ちなみに、日本企業が「共同体」的であるということは、1970年代頃から社会学者の小室直樹や作家の山本七平らによって指摘されてきた。共同体という言葉はドイツ語の「ゲマインシャフト(Gemeinschaft)」に由来する。小室らの主張は次のようなものである。資本主義下の私企業とは、ある共通の目的を遂行するための機能的組織(ゲゼルシャフトGesellschaft)なのだが、日本ではなぜか会社が村落共同体や血縁共同体のような、生活共同体であり運命共同体的になってしまう。それはムラ的であり、イエ的でもある。
では、以前のドイツ企業は「サラリーマン共同体至上主義」だったのだろうか。そもそも共同体という概念はドイツから来たから、ドイツ企業もそうだと考えてよいものか。恐らく違うと思う。その最大の理由は、ドイツは日本に比べ、会社という「タテ」のつながりよりも、資格や職業という「ヨコ」のつながりを重視する傾向が強いからである(中根千枝「タテ社会の論理」)。だから、取締役会にブルーカラーの代表者(労働組合のトップ)が入るのだ。
このように、ドイツと日本の文化的背景の違いを考慮していない点は気になるが、日本企業の稼ぐ力を高めるためにガバナンス不全を克服すべきという主張には同意である。そして、その答えは米国型の株主主導によるコーポレートガバナンス(プリンシパル=エージェント理論など)にはないだろう。この考えに立てば「経営者は株主のエージェント(代理人)であり、ゆえに株主の利益を最大化するために動くべし」となるが、こうした考え方には「致命的な欠点がある」と指摘している。なぜなら、法人としての企業はモノであると同時にヒトであり、株主はモノとしての企業の所有者であるが、ヒトとしての企業は株主の所有物ではないからだ(岩井克人の法人論)。本書が提示する「ステイクホルダー主義に基づくエクイティガバナンス」という中庸的な発想は、これと合致する。、、、、」